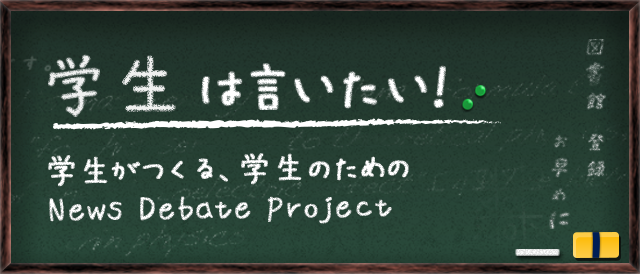大阪の女子生徒が生まれつき茶色の髪を黒染めするよう強要された問題について、今日の新聞に次のような意見がありました。
こうしたメンタリティーは、しかし学校だけの話だろうか。むしろ、日本社会自体の不寛容さや「出る杭(くい)」を押さえつける傾向を、学校は正直に映しているだけなのかもしれない。
私の通っていた学校にも、何のためにあるのかわからないルールがたくさんありました。例えば、学校の規則としてはヒールの高いローファーを履いてはいけない、体育の授業で穿く靴下の色は白色に限る、など。生徒間では、ある部活動では下級生がジャージの首元のチャックを一番上まで締めなければならないなど、暗黙のルールがありました。なぜそれが必要なのか、と理由を聞いても、誰も納得のいくような答えを持ち合わせていなかったでしょう。大学などで自分の母校の話をすると、校則の寛容さは学校によってかなり差があるのだなといつも感じます。
社会に出たら理不尽なことが山のようにある。それを我慢するための訓練を学校でするのだ、という人がいます。反抗心を抱きながら、自分も「そういうものなのだ」と窮屈さをやり過ごしていた一人でした。学校は集団内での立ち振る舞いも学ぶ場です。性格もバックグラウンドも違う子どもたちが集まっている多様な空間であるとも言えます。
しかし、そこがあまりにも強力な規則で縛られていたら、生徒たちは一律であることが美徳だと思うようになるのではないでしょうか。そのような集団では、真の多様性は発揮されようがありません。
世の中、すべてが思い通りにいくわけではないので、「そういうものだ」とやり過ごすスキルも必要でしょう。しかし、それが習い性になってしまうと、本当に理不尽な問題にノーと言えず、疑問すら持たないうちにすり切れてしまうのではないかと危惧しています。新たな価値観が生まれなければ、社会の発展も停止します。話が飛躍してしまいましたが、規則ばかりを押しつけるような学校はそうした危うさを孕んでいると思います。
いま、日本の「ステレオタイプ文化」に変化が起きています。女性の生き方や子どもの教育、働き方改革を筆頭に、新たな選択肢や改善を求める動きが絶えません。その中で、これからを担う若者を育てる教育現場が「出る杭は打たれる」社会の縮図なのだとすれば、まずはそこから一歩抜け出す必要があるのではないでしょうか。
社会学者の大澤真幸氏は、著書「不可能性の時代」において、敗戦後にアメリカ軍に一年間拘留された、映画監督の小林正樹氏の発言を次のように解説しています。
日本社会が、あまりの短期間に大きく変化することができたのは、実際には、何も変わっていないからではないか、と小林は疑念を抱いているのだ。
価値観の多様性を保ち、新しく有用なしくみが妨げられずに作動するよう調整を繰り返して、私たちの社会が次のステップに進むことを願っています。
参考記事: 3日付 日本経済新聞朝刊(東京13版)1面(総合)「ポスト平成 新しい日本へ(中)多様性がひらく強い社会」