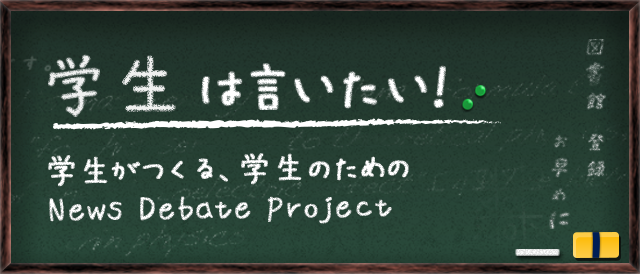今年は7月2日から9月23日の3か月足らずしか見ることのできない嵐山の鵜飼(うかい)。屋形船から嵐山の夜景と鵜飼を楽しむ、そんな夏の風物詩を筆者も堪能してきました。「それいけそれいけそーれいけ」という掛け声。「ドンドン」とリズムよく響く、鵜匠が舟を叩く音。松明の光が赤く燃え、5羽の鵜が勢いよく川に潜ります。幻想的な世界に魅了されました。
船の上から松明の火で川面を照らし、紐で括った「鵜(う)」に鮎を捉えさせる鮎漁が鵜飼です。鵜が丸のみにした魚を鵜匠が吐き出させると、ぴゅうっと魚が宙を舞います。うまく吐き出させるには熟練の技が求められます。魚のうろこの向きを吐き出す方向と合わせるため、鵜匠は鵜が頭から吞み込んだ魚を胃の中で一回転させ、頭を上にした状態で吐き出させるそうです。ここには非常に繊細な技術が必要だと屋形船の船頭さんが教えてくれました。松明の火で川面を照らすことで魚のうろこが光り、鵜が見つけやすくなるようです。そのため、雨で松明が点かない日と松明の火が目立たなくなる満月の夜は休みます。
鵜飼が続いているのは全国で11カ所です。岐阜の長良川が有名ですが、京都なら嵐山と宇治、福岡県の筑後川、大分の三隅川、山口県の錦帯橋の下、愛媛県の大洲、愛知の木曽川、山梨県の石和、広島県の三次。岐阜県では小瀬でも見られます。どこか一カ所は聞いたことがあるのではないでしょうか。
嵐山の舞台は大堰川です。平安時代、清和天皇の時代に宮廷鵜飼として始まりました。京都の公家たちが、夏の暑さから逃れるために船の上で楽しむようになったともいわれています。ちなみに大堰川は上流を保津川、嵐山の渡月橋を挟み下流を桂川と呼びます。最後には淀川に合流するという、何度も名前を変える川です。
現在鵜匠は全国で66人いますが、そのうち岐阜県長良川の鵜匠9人だけは国家公務員、宮内庁式部職鵜匠です。江戸時代の初めは29人、明治の初めで17人いたそうです。減った理由は、男性一人しか跡取りができない「一子相伝」を守っているから。「これからは減るばかり」と船頭さんは話してくれました。では嵐山の鵜匠は誰が務めているのか。船頭さんや漁業組合の方が担当されているようです。文頭にも書きましたが、鵜飼の時期は約3か月と非常に短く、さらに給料も限られているようで、こちらもなり手が減っているそうです。鮎が川に戻ってくる時期が決まっているから期間が限られてしまうのです。自然の中での行事だからこその訳がありました。
さらに驚くべきことを船頭さんが漏らしました。「川が年々浅くなってきて困っている」というのです。屋形船を浮かべることが非常に難しくなりますし、なによりも、鵜が鮎を取るために川に潜る際に頭を打ちます。台風や大雨の影響で上流から土砂が運ばれ、大堰川周辺に堆積した結果、年々水位が低くなっているようです。船頭さんは4メートルある櫂(かい)の川面から出ている部分が長くなっていることでこの現象を実感しているようです。「土砂を運び出してほしいんだけど、国に言ってもなかなか対応してくれない」と嘆きも聞こえました。
平安から続く非常に長い歴史を守ろうと努力する人々がいる一方で、続けられる環境は整っているのでしょうか。後継者の課題、川の水深の問題、一学生の筆者にできることはほぼゼロといっていいでしょう。文化を体験する私たちはその歴史や現状、関わる人々に触れることで、彼らが抱える熱い思いや課題を身をもって感じ、こうした形で発信することしかできないのでしょうか。もどかしさを覚えました。
参考記事:
8月22日付 読売新聞オンライン 「鵜飼観光船船頭への道 初の研修会 歴史学ぶ」