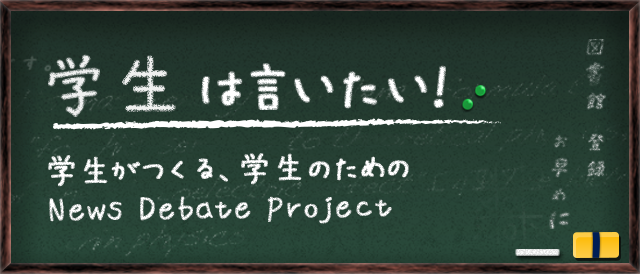名前は個人を特定するものであり、生まれた時からの名はアイデンティティーでもある。平均初婚年齢が30歳前後となった現在では男女とも婚姻前にキャリアや信用、人脈、資産を積んでおり、改姓に伴う負担は大きい。
企業経営者らは「名字の変更や使い分けに対する負荷をビジネスの現場に押しつけており、企業の生産性を下げる一員となっている」などとしてこの春、「選択的夫婦別姓の早期実現を求めるビジネスリーダー有志の会」を発足させた(日本経済新聞)
24日各紙朝刊の紙面を大きく占めた、夫婦別姓訴訟「合憲」のニュース。合憲とした裁判官らが「司法府ではなく国会が判断すべきこと」と結論付けたのに対し、三浦裁判官は「憲法上の保障に関する問題であるから司法の責任で判断すべき」との意見を述べています。専門家からも「人権を守る最後の砦としての司法の役割を放棄した」(早稲田大・棚村教授)などと批判の声が上がっています。
果たして、私たちは司法権の限界をどう捉えるべきでしょうか。
司法が踏み込まない理由は、日本の最高裁の「司法消極主義」の考え方にあります。戦後に憲法81条で、司法による違憲審査制を導入して以来、最高裁大法廷による違憲判決の数は10件のみと、ごく少数にとどまります。基本的に「法律に明白な誤りがない限り、裁判所は介入すべきではない」という考え方に立っています。
国会は、国民によって選ばれた代表によって構成され、内閣は国会で指名された内閣総理大臣と総理が任命する国務大臣によって組織されています。一方、裁判官は国民によって選ばれた者ではないため、裁判所は民主主義における直接の基盤を持ちません。違憲判断を下すということは、議会の判断を無効にすることと同義であるため、司法には十分な慎重さが求められるのです。
しかし、それと同時に求められているのは、国民の救済です。国会審議の促進を求める意見書が提出されたり、国連の女子差別撤廃委員会から法改正などを勧告されたりしているものの、動いてこなかった立法府。夫婦が別の姓を選ぶことができる制度を導入する法改正案は、1996年にまとまっていましたが、自民党内の反対意見に阻まれて国会への提出さえできませんでした。国民の基本的な人権がないがしろにされたままの状態に対して提言するのは、司法府の重要な役割のはずです。長年に及ぶ訴えである今回の件は、国会の判断を待つより、司法の立場で合理的な判断を下すべきだったと思います。
合理的な判断に関して、今回の判決には次のような文面がありました。
婚姻や家族に関する法制度は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における様々な要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての総合的な判断によって定められるべきだ。したがって、夫婦の姓に関する法制度は国会の合理的な立法裁量に委ねられている。
しかし、この「国の伝統」や「国民感情」が、現段階でそれほど重視されるべきことなのかも疑問です。選択的夫婦別姓制度の導入により、「国民の福利が向上するか減少するかを比較するのが有用」とする、草野裁判官のようなより具体的かつ合理的な検討がなされるべきだったのではないでしょうか。合憲派は「民法750条の規定を『合憲』とした2015年の最高裁大法廷判決の趣旨からも明らかだ」としていましたが、現在の社会情勢を踏まえた、具体的な論拠を示して欲しかったと思います。
今回の合憲判決を受け、司法の役割、三権分立の在り方があらためて問われているように思えます。私たちの人権を守るために、統治機構の仕組みについて疑問を持ち、一国民としてその運用に目を光らせていく姿勢を大切にしたいものです。
参考記事:
24日付朝日新聞朝刊(愛知14版)1面「夫婦別姓 最高裁また認めず」関連記事2、10、29、31面
24日付読売新聞朝刊(愛知13版)1面「夫婦別姓 再び認めず」関連記事3、4、11、33面
24日付日本経済新聞朝刊(愛知12版)2面「社説 夫婦別姓の議論を国会に促す最高裁決定」関連記事39面
参考文献:
辻村みよ子『憲法 第6版』2018年 日本評論社