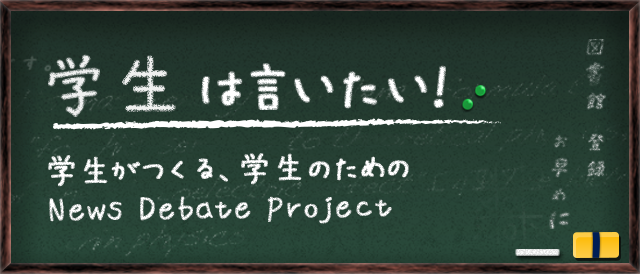映画×ジャーナリズムの第三弾です。今回は『クライマーズ・ハイ(2008)』を紹介します。この作品は、日本航空機123便墜落事故を新聞社の視点から描き、報道の重要性や記者の責任、そして人間の強さと脆さを鮮明に映し出しています。
1985年8月12日、日本航空機123便が群馬県多野郡上野村の御巣鷹山に墜落しました。物語の舞台は、群馬の有力な地方新聞社です。主人公の記者・悠木(堤真一)が事故の取材と出稿を取り仕切る全権デスクに任命され、会社内外の軋轢に葛藤しながらも未曽有の事故を伝えるために奮闘します。
映画では、社内の様子が忠実に再現されています。共同通信からの速報が「キーンコーンカーンコーン」という音とともに社内に流れる様子や、午前一時の締め切りに間に合うように必死に記事を書いている記者の姿が描かれ、映像を通してもリアルに感じられました。
一番驚いたことが、現場とデスクとの連絡手段です。当時はスマートフォンのような便利な通信機器はなく、ガラケーすら普及していません。事故が起きたのは18時56分でした。速報を受けて現場に向かった社会部の記者二人(堺雅人・滝藤賢一)は、泥だらけになりながら山を登り取材を行います。原稿の締め切りの1時がすぐそこまで迫る中、連絡手段は山を下り民家に電話を借りるという原始的な方法でした。この緊迫した場面で、堺雅人の演じる佐山が電話に語りかける言葉一つひとつに重みを感じ、やはり現場を見た記者が紡ぐ言葉こそ読者の心に訴えかけるのではないかと思いました。
タイトルの『クライマーズ・ハイ』は物語の核心を捉えるキーワードになっています。この言葉は、登山者の興奮状態が極限まで達し、恐怖感がマヒしてしまう状態を指します。悠木は山登りが趣味であり、作中でも何度か登山の光景が挿入されています。
新聞記者は事件・事故が発生したらすぐに現場に駆け付けますが、スクープを出そうと無我夢中になると、山登りのように恐怖感がマヒする状態に陥り、周りが見えなくなってしまう。作中では、このクライマーズ・ハイという言葉が、事故発生直後から記者たちが取材に熱中し高揚していく危険な姿と重なります。そうなる前に、裏付けや調査をぬかりなく行い、それを踏まえて報道するという姿勢が求められていると解釈をしました。
朝日新聞によれば、原作の著者である横山さんはこう話したといいます。
あの日、あの現場では、私の知るすべての形容詞と慣用句と言い回しを駆使しても御巣鷹を描写できなかった
この言葉に出遭ったとき、これほど事故現場がいかに悲惨であったかを表す言葉はないだろうと、衝撃を受けました。横山さんが現場で感じた無力感は映画にも描かれています。悠木は極限の精神状態の中で、真実、命の重さ、上司と同僚、そして地方紙の役割と対峙します。
他社との特ダネ争いなど、事故報道すら手柄にしたいと考える記者や権力にすり寄る報道機関を描き、綺麗ごとの物語で済ましていません。あの日の現場に行き、感じたことがそのまま作品に反映されているのだと感じました。
筆者はこの作品を観たことで改めて史上最大の航空事故と呼ばれた日本航空機123便墜落事故について調べました。映画には歴史を伝えることで、更に深堀りしたいと一歩を踏み出すきっかけを与える力があると考えます。事故から今年で39年が経ち、当時の出来事を知らない世代が増えています。風化させないためにも親しみやすい映像メディアの果たす役割は大きいのではないでしょうか。
参考記事
2023年8月12日付 読売新聞 夕刊 社会 9頁「御巣鷹へ遺族ら登山 日航機墜落38年 墓標に『元気だよ』」
朝日新聞デジタル 「記者が感じた『クライマーズ・ハイ』 野心と苦い思い出」
参考資料