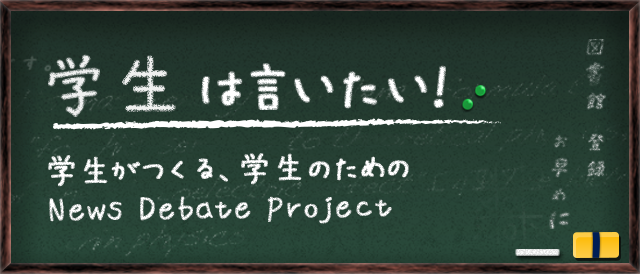この投稿をお読みの皆さん、少し想像してみて下さい。
わが子やご家族と住まいを火災で失い、悲しみに暮れている中、その罪を問われ投獄され、その後20年を塀の中で過ごす日々。「ぞっとする」や「考えたくもない」のような簡単な言葉では言い表せない気がしてなりません。今日は実際にそのような立場にあった方の事件から裁判や捜査の在り方を考えていきたいと思います。
26日午後、大阪市東住吉区の小6女児が死亡した住宅火災で無期懲役とされ、再審(裁判のやり直し)認められた後も服役していた青木恵子さん(51)と朴竜晧さん(49)が逮捕以来20年ぶりに釈放されました。大阪高裁は同日午前、刑の執行停止(釈放)を認めた高裁決定を支持し、検察側の異議申し立てを棄却しました。この事件は95年7月、青木さんと朴さんの自宅で火災が起き、入浴中の長女めぐみさん(当時11)が焼死し、生命保険金目的の放火殺人事件として2人が逮捕、起訴されたものです。捜査段階で容疑を認めたとされましたが、裁判では無罪を主張していました。06年に最高裁で、無期懲役判決が確定しています。
「やっと当たり前の世界に戻れた。」 「自由の身になり、感無量。」(朝日)
これは、釈放直後の青木さんと朴さんの言葉です。この言葉をテレビや新聞で見ている我々にと取ってみれば、当たり前の世界にいることをここまで嬉しく感じさせるほどの苦難をお二人が経験したということでしょう。そのような経験をさせてしまった原因として、捜査上の不手際や裁判の流れが挙げられます。この事件では、2人が自宅車庫にガソリンを撒いて放火した疑いが持たれていましたが、弁護側の検証実験により、車庫の車からガソリンが漏れ、そのガソリンが自然発火した可能性があることが判明し、その実験結果が釈放が認められる大きな要因となりました。また、有罪が確定した当時の根拠として、捜査段階の自白が決め手となっていましたが、裁判では一転無罪を主張していました。このことから、捜査段階で自白の強要があったのではないかとも考えられます。捜査の初期段階でお2人が疑われてしまうことは仕方がないでしょう。しかし、放火という見立てに固執せず、弁護側が指摘したガソリン漏れの可能性などについても検証を行えば、お2人への疑いは晴れていたかもしれませんし、その人工的な「証拠」に加え、「自白」が重なれば、検察は容易に起訴できます。被疑者には逃げ場がありません。
では、ここからが本題です。まさに「筋書通り」という仕組みが裁判にあっていいのでしょうか。いいはずがありませんよね。警察はマークした人物を何としても拘束しようと厳しい取り調べを行います。そこで得た「証拠」をもとに検察が起訴し、有罪や重罰を主張します。弁護側は無罪を主張したり、現行犯等であれば、執行猶予や大幅な減刑を狙い、裁判所が判決を下すというのが流れでしょう。このような流れもあってか、現在日本の逮捕された容疑者が起訴される割合は9割を超えています。もちろんこの数には現行犯も含まれていますし、明らかに疑いのない人間はそもそも逮捕すらされていないため、一概には言えませんが、先ほども述べた通り、何が何でも拘束し、有罪を目指す姿勢が今回のような冤罪を生む原因になっているように感じざるを得ません。裁判はそのような出来レースをするのではなく、被疑者が本当に罪を犯したのかについて、裁判所、検察、弁護士の三者に加え、警察を含めた四者が協力して、真相を明らかにしていこうという姿勢が求められるのではないでしょうか。いつまでも検察・警察連合VS弁護士というようなかたちでは、明らかに前者優位で、今回のような悲劇を今後も生み出す原因にもなりかねません。また、このような考え方を基準にすると、酌量の余地のないような者を必死に守る弁護側の姿勢も一部改める姿勢も今後求められると考えられます。
今回の事件はまだ無罪が確定したわけではなく、あくまで刑の執行停止ですが、同様のケースとしては、1950年の足利事件で逮捕された菅谷利和さんが2009年に釈放された映像が思い出されます。彼は当時の刑事や検察、裁判官の実名を挙げてでも土下座させてやりたいと怒りを込めた言葉を発していました。罪のない人を拘束し、刑罰を科すということはそれくらい恐ろしいことです。事故や過失もありますが、犯罪というものは犯人が行うもの、犯人が生み出すものです。捜査や起訴で作りだされることはあってはなりません。そして有罪の決定を下すのはあくまで裁判所です。裁判員制度などの改革を行う前に、裁判やその前段階の改革をすべきではないでしょうか。
市民感覚を用いる前に、関係者に当たり前の感覚を持ってもらうことが先のはずです。
参考記事:27日付各紙関連面