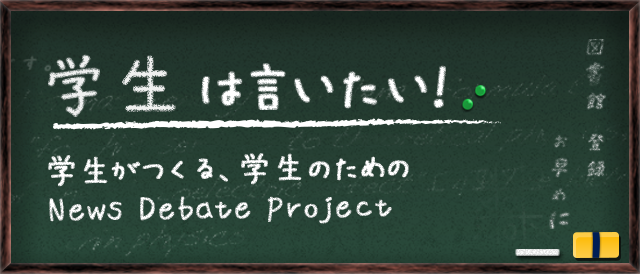■平和的象徴にとどまらない戦争遺産
8月9日、長崎市の爆心地公園に向かった。天気予報は曇りと言っていたが、台風一過で晴天となった。蝉の声が鳴り響く中、爆心地公園は政治団体や市民集会が平和の訴えをしていた。主要紙や地元紙の記者は植え込みの縁に腰かけ、忙しそうにパソコンを打っている。普通の公園とは明らかに違う物々しい空気、筆者にも緊張が走る。
この公園はその名の通り、1945年8月9日の爆心地に位置する。園内には高さ6.5mの原子爆弾落下中心碑があり、人々がひっきりなしに手を合わせる。その周辺ではテレビ局やラジオ局のクルーがインタビューする人を探していた。
その様子を少し離れたベンチから遠目に眺める女性がいた。少し話を聞いてみた。女性は佐賀県で生まれ、幼いころに長崎に移り住んだ。子どもの頃、爆心地公園近くの小売店に行った際、店の人が「そこ(公園)の土をちょっと掘り返せば骨が出てくるよ」と言ったことが衝撃的で今でも頭から離れないという。
女性は続ける。少なくとも1967年ごろまでは毎年4月に爆心地公園でお花見が行われていた。しかし、どんちゃん騒ぎとなって酔っ払いが近くの交番に押し掛けるトラブルが発生。被爆者の遺骨の上での酒盛りは好ましくないとのことから、ここでの宴会はなくなった。
女性は長年、長崎に住んでいるにもかかわらず、原爆の日にここに来るのは初めてだそうだ。理由を尋ねると、「被爆者のための場所だから、行っちゃいけないという思いがあった」。「来てみてどうですか」という筆者の質問に、「ここで拡声器を使って平和を訴えることは大事だし、正しか事ば言っていると思うとですけど、今日ばかりは亡くなられた方々のために静かにするのが良いと私は思うとですよ」。
この女性は職場の上司の一人が被爆者だった。ただ、そのことを本人から聞いたわけではない。被爆体験をまとめた文集を読んだ際、そこに名前があったのだ。「こんな過酷な経験をされていたとは全く思いませんでした。ただただ驚くしかなかったです」。
人というのは自分から苦しい過去を話したがらない。「つらい過去に踏み込んでしまっていいのか、思い出させてしまっていいのかと思い、こちら側から動き出せなかった。でも、聞けば話してくれたかもしれない。家族を失った上司の孤独を思うと悔やまれるとです」と女性は語った。
公園内のベンチに座っている高齢の男性にもお話をうかがった。この男性は終戦後に大陸から引き揚げてきて以降、ずっと長崎に住んでいる。50年近く、毎年原爆の日にはここに足を運び、じっと座って平和への意思表示をしてきた。当初は立錐の余地がないほど人であふれていたという。男性はここに通い続ける理由を「日本人の一人として、いた方が良いと考えている。あんまり偉そうなことは言えんとですけど」と話す。
男性は自身を含め兄弟全員ががんになった。原爆投下後の残留放射線の影響と考えている。「原爆の被害を受けたのはその場にいた人だけでなく、自分のような引き揚げ者もいる。ただ、直接の被爆者の輪の中に自分のような被爆者は入りづらい」と話した。
筆者はこれまでにも何度か長崎の爆心地公園やその隣の平和公園を訪れたことがあり、ほぼ毎年、原爆の日の平和記念式典の様子をテレビ中継やニュースなどで見てきた。爆心地公園や8月9日という日付が平和の象徴的存在だと考えてきており、今もそう思っている。ただ、公園が多くの人にとって「最期の場所」であり、8月9日が何万もの人の「命日」であるという感覚があまりなかった。
今回、爆心地公園で6人の方に取材した。原爆が被爆者の人生をいかに狂わせたのかを長崎の人たちが身近に見聞きしており、そのため爆心地公園や原爆の日を平和の象徴以前に被爆者の人生の一部として捉えているように感じた。他県出身の筆者以上にこれらを近寄りがたい存在と考えているような気がした。
戦後76年経った今も先の戦争の遺産は全国にあまたある。それが戦争に対する教訓、反面教師としての役割を果たすことは間違いない。ただ、それらを何か特別なものとして済ましてはいけないだろう。そこには多くの人の生があった。そのことを感じ取ることで、平和を希求する思いを強くできるのではないだろうか。今回の取材を通して、黙祷の本当の意味を知った気がした。
参考資料: