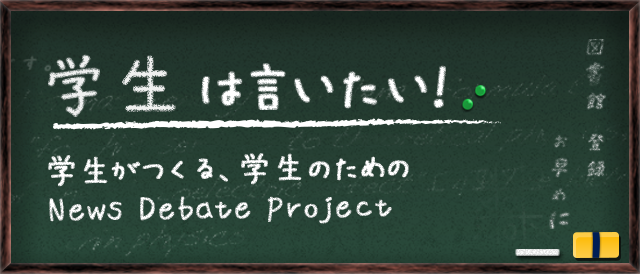3月は異動の季節。本日付の朝刊には、この1年を振り返る新人記者のコラムが掲載されていた。
「記者になって初めてのこの1年、県内で震災関係の取材を多く経験した。写真や映像だけでは分からない圧倒的な現実に言葉を失った」
朝日新聞仙台総局の和田翔太記者は、初任地・宮城での記者生活をこう綴った。未だに解決しない震災関連の訴訟、亡き人への想いを抱き続ける遺族。和田記者にとって、被災地の現状はどれも印象深かったのだろう。

▲児童と教員84人が犠牲になった石巻市立大川小学校。同小の損害賠償訴訟を取材した和田記者はコラムで「遺族の思いを受け止めきれず気持ちが高ぶり、会見場を出てしまった」と省みた。2018年7月30日、石巻市で筆者撮影。
和田記者のコラムを読み、私は自らの8年間を振り返った。思えば私は、震災から逃げ続けてきた。
あの日、仙台市内の自宅で激しい揺れに襲われた。幸い自宅の被害はなく、親類も友人も無事だった。停電は3日経つと復旧し、物流が回復した4月頃には震災前の生活が戻っていた。しかし、復旧が進むことを素直に喜べなかった。沿岸部ではまだ、体育館や仮設住宅で暮らす人たちがいた。家も家族も失っていない自分に後ろめたさを覚えた。食べることが申し訳ない。電気を使うことも申し訳ない。笑うことが申し訳ない。日常生活のあらゆる行動に罪悪感を抱いた。その気持ちは震災後数年間、消えることはなく、自ら被災地に足を運ぶことも、話を聞くこともなかった。
風向きが変わったのは大学進学後。関東に出ると、驚くほど震災の話題を見聞きしなくなった。故郷では震災報道を目にしない日はない。思わず「震災の時は何をしていたのか」と大学の同期たちに尋ねた。すると返ってきたのは「覚えていない」「さすがにもう復興したでしょう?」。唖然とした。まだ、故郷に帰れない人もいるのに。
東北の今を伝えたい。
同期の言葉を聞いて以降、「何も失っていない自分」への後ろめたさは次第に「何も知らない自分」へのもどかしさに変わっていた。今は月に1度は宮城へ帰省し、沿岸部で語り部の方から話を聞いている。
以前、広島で被爆者の方から「私にも君にも伝える責任がある」との言葉をいただいたことがある。平和を維持するためには、過去の出来事を語り続ける必要がある。だから我々には「伝える責任」があるのだと。
恐らくそれは災害にも通ずる。過去の教訓を伝えていけば、次世代の命を守ることができる。私たちの先祖は石碑や地名を用いて、それを試みてきた。次は私たちがそのバトンを受け取る番だ。
和田記者はコラムの最後をこう締めくくった。「異動先でも震災報道に関わっていければ」
伝承の担い手である記者の意志は、頼もしい。
参考記事:
23日付朝日新聞朝刊(東京12版)32面(地域面宮城版)「経験という財産携え異動先へ」(和田翔太記者)