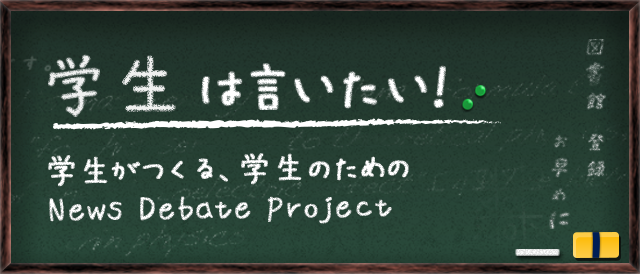春の訪れを告げるかのように、17日東京で桜の開花宣言が発表されました。言わずもがな、桜は古くから人々に親しまれ、私たちの心とともにあり続けてきた存在です。これまで数々の和歌に登場していますが、中でも印象的な歌が伊勢物語に残されています。
「世の中にたえて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし」(この世の中に桜というものがなかったら、春をのんびりした気持ちで過ごせるだろうに)
美しく咲き誇り、儚く散る桜に心煩わされる。一見、不満のようにもとれますが、ここには筆者の桜に対する賞賛と愛着の念が表れています。胸騒ぎのような、何かが始まる予感のような、そんなそわそわした感覚を春が来るたび感じずにはいられません。
とりわけ新生活が始まる人は、期待と不安で心穏やかではないでしょう。進学する人も就職で社会に出る人も、新たな環境に適応できるか、社会でどう生きていくか、それぞれが思いを巡らせていることと思います。
人間は社会的な生き物であり、一人一人が社会や集団を作っています。「わたし流」だけで生きようとすれば、仲間や社会とぶつかってしまう。一方で、集団に合わせすぎれば、全体のために個人を犠牲にしようとする考えに陥ってしまう。
「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。」
個人の自由か、それとも社会の一員としての役割か。夏目漱石は自身の著書『草枕』の中で、二者の衝突に対する苦悩を綴っています。
情報化とグローバル化が進行する現代において、今後ますます「個人の自由」が求められることでしょう。利己主義の広がりが社会の危機を招くことも想像されます。仏の経済学者・思想家のジャック・アタリ氏は、自身の著書『危険とサバイバル』で「新しい個人主義」を提唱しています。自分自身を大切にすること。その上で、他人を尊重する共感力を磨くこと。彼が主張する7原則の一部です。
ところで、冒頭で紹介した和歌には、返歌があります。
「散ればこそいとど桜はめでたけれ 憂き世になにか久しかるべき」(桜は惜しまれて散るからこそ素晴らしいのだ。憂の多いこの世に永遠のものは何もないのだから。)
短命な桜に見る人の世のもの悲しさ、諸行無常さを歌っています。たしかに世の中は刻一刻と移り変わりますが、「社会と個人」の関係は夏目漱石の時代からそれほど変わっていないような気がします。先人たちが思いを馳せた桜を前に、改めて社会との向き合い方を考えてみるのはいかがでしょうか。
参考:
19日付 日本経済新聞朝刊(東京)19面「社会でどう生きるか」