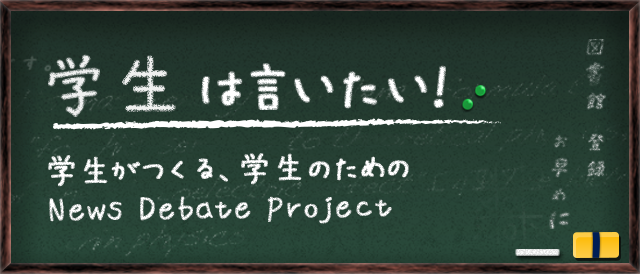ついこの間、半年ぶりに実家に帰りました。母の手料理を楽しみにしていましたが、もうひとつ、とても楽しみにしていたものがあります。
それは、父の本棚です。
ジブリ映画の原作や、数々の専門書、日本の神名辞典なんてものもあります。子どもの頃から、父の書斎の床に座り込んで、ずらりと並べられた本の背表紙をじっと見ている。その時間が好きでした。その記憶からか、紙の本はいまでも大好きです。
さて昨今、書店業界の不況が騒がれます。インターネットの普及に後押しされた電子書籍ビジネスの拡大により、大手書店であっても経営難に陥ることもしばしば。私の周囲でも、全国展開の大型書店がある日突然、店を畳むといったことが多くなった印象があります。個人の小規模な書店はその比ではありません。このような状況では、新規参入が少ないのも仕方ありません。出版物の販売額はピーク時に比べ、半分以下にまで落ち込んでいるようです。
そんななかで、ある信念のもと、若くして新しい書店を立ち上げたひとがいます。
30代で東京都に、書店「「双子のライオン堂」を出店した竹田信弥さん。書籍の販売は、なんと高校生の頃から。インターネットでの古書販売が始まりだそうです。 彼の信念は、「本当にいい本は、いい書店は、たとえ出版業界がどうなろうともいつまでも残り続ける」。それを証明するために、自信の書店を100年先まで残したいといいます。
いま、若者の活字離れが騒がれています。けれど、どんなに活字が苦手なひとでも、いい本や、いい文章にひとたび触れれば、なぜ本好きが紙の本にこだわるのかきっとわかるはずです。
確かに、インターネットで手軽に見られる漫画や小説、雑誌は便利です。かくいうわたしもよく利用します。それでも、書店に向かうときの高揚感や、本を手に取ったときの満足感はインターネットでは得られません。
それに、眠りにつく前に読むお気に入りの本が液晶画面の向こう側では、ちょっと眩しすぎるでしょう?
参考記事:
8日付 朝日新聞朝刊(大阪10版) 13面(オピニオン) 「薄利多売のモデル 限界に」