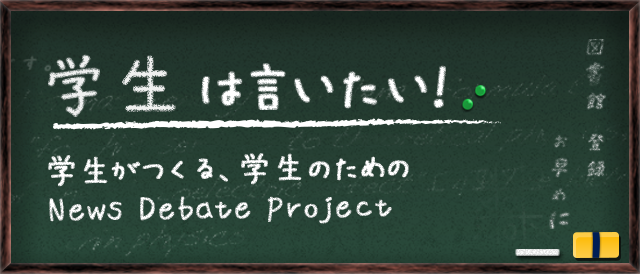「6三銀は自重しすぎですか?」「いやいや、ある手だと思います。ただ、いきなり8五桂から仕掛けられてもわからなかったです。」
やはり対面で指す将棋は格別に面白い。つい先日学園祭の将棋ブースでお客さんが来るまで、母校中大の将棋部で1番強い奨励会三段(四段からプロ)の部員に指導対局をしてもらえた。1回も勝つことはできなかったが、細かい部分まで教えてもらえて確実に棋力が上がった。
三手一組の好手順があったので感想戦で詳しく聞くと、「AIで調べてたら見つけたんです」と教えてくれた。AIは普段から使うのかを尋ねると、「振り飛車党の中では相当使う方だと思います」と笑いながら答えてくれた。プロだけでなく奨励会の世界にもAIが浸透していることを痛感した。
11月2日に英国でAI安全性サミットがあったからか、直近はAI関連の記事が各紙で増えたような気がする。10日付の朝日新聞朝刊では、佐藤天彦九段のインタビューが記事になっていた。
佐藤九段はファッションやクラッシック音楽、建築や西洋美術にも造詣が深く、ついたあだ名が「貴族」。趣味だけでなく立ち振る舞いも優雅で、将棋にも美的センスや作品性を意識するほどだ。
また、これは筆者個人の感想だが、佐藤九段は棋士の中でも言語化やトークに秀でていることは間違いない。他のインタビューでも言葉の選び方に独特の感性がにじみ出ていて、将棋以外の部分に魅了されるファンも多い。
特に記事の中で印象的だった表現が「おいしい文脈をAIは学習できません」だ。数値に還元されすぎると、対局の文脈の豊かさが抜け落ちてしまう。その場における最適解や人間の意図を離れた論理だけでは、将棋は成り立たない。
棋は対話なりという言葉があることからもわかる通り、話さなくとも指し手を見れば相手が何を思っているかわかる。「そんな切り口がありましたか」「それは図々しすぎるので許しませんよ」「やるならやってきなさい」。対局中には綺麗な駒音だけが響き続け、盤を挟む2人の様子は静寂そのものに映るが、両者にしか見えない世界で火花が散るほどの激しい対話が交わされている。
もちろん、プロはアマとは違い勝ってこそという性格から逃れられない。それでもエンタメや文化として見る人を引きこみ、先人たちから受け継がれてきた時間的繋がりの中に身を投じる必要もある。局面の最善でないとしても盤を挟む2人だけが作り出す偶然性や一回性を希薄にしない人間性と、人間にはない感性で新たな可能性を模索するAI性。双方が織りなす共鳴や葛藤の最前線が将棋の世界にあると、今回の記事で改めて感じた。
参考記事:
10日付 朝日新聞朝刊 13面(オピニオン) 「盤上の対話から見えるもの」
10月29日 朝日新聞デジタル 「佐藤天彦九段、なぜ四間飛車を採用? 名人経験者対決 順位戦観戦記」 佐藤天彦九段、なぜ四間飛車を採用? 名人経験者対決 順位戦観戦記:朝日新聞デジタル (asahi.com)