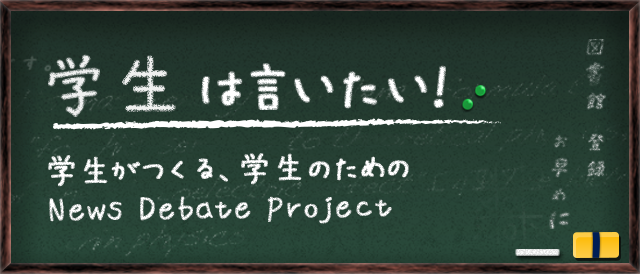この文章は他のものと違う。読み終わった瞬間に確信した。きっと筆者もこんな文章が書ければ、将棋の記事を書く度に頭を抱えることもないだろう。ほんの少しだけ妬みがないわけではないが、それを遥かに上回る驚きと感嘆がそこにはあった。
9月3日に日経電子版に掲載された、逢坂剛さんの王座戦第1局の観戦エッセーを読んだ。逢坂さんは筆者の通う中央大学の先輩で、かつ文章の書き手としても大先輩だ。そんな方の文章を、今回はおこがましいことこの上ないことを承知の上で、どんな点に注目して読んで欲しいか勝手に紹介したい。
文藝春秋が2021年から1年に1回発行している『読む将棋』という雑誌がある。そのコーナーの1つに「将棋記者」のおしごとというものがある。そこで将棋担当をしている朝日新聞の村瀬記者、読売新聞の吉田記者、東京新聞の樋口記者の3人が揃って、難しいことに「将棋の魅力をいかに書くか」ということを挙げている。
今回の逢坂さんのエッセーは、推理作家らしく将棋をミステリーのように描いているのだが、これがあまりにもピッタリの表現なのだ。
どのような経緯でそうなったか分からないが、まるで極上のミステリーのように、ジグソーパズルの最後の一片がぴたりと合った、という充実感に包まれたのだった。
将棋の1局の平均手数は115手と言われており、各局面での可能な手数が80手程度であることから、80の115乗で10の220乗くらいパターン数が存在すると言われている。もちろん、プロは一瞬でほとんどを切り捨て最善に近い数手をじっくり考えるので、このパターンの全てを考慮しているわけではない。それでも大きく形勢が動く中盤の5〜10手を、それぞれ3候補手ずつ読んでも少なくとも200〜60000手という計算になる。
中盤ではこれだけ膨大な数になり、かつトッププロが1手に長ければ2時間強かけても正解がわからないような複雑さのはずなのに、当たり前だがどの対局にも終わりがある。しかもプロの投了図は本当に美しい。最初からそうなることが決まっているような気さえしてしまう。それは日経電子版記事の見出しの通り「極上のミステリー」という言葉がよく似合う。
またこの記事のすごいところは表現がピッタリなだけではない。とにかく将棋がわからない人にもわかりやすい。
戦型の名前も出てこなければ、両棋士の対局中の雰囲気すら書かれていない。ただひたすらに逢坂さんの将棋好きぶりと、控え室での当人の局面への熱中ぶりに焦点が当たっている。いわゆる「観戦エッセー」とは違うかもしれないが、将棋の魅力も存分に伝わるし、読み切らせる力のある文章になっている。
「自分にしか書けない切り口」「わからない人にも伝わり、わかる人にはより伝わる」「何より筆者本人が楽しむ」。この3つが揃った、自分が目標にしているような将棋記事の理想型を見たような気がした。いつかこんな記事を自分も新聞に載せたい。
参考記事:
3日付 日経電子版 「まるで極上のミステリー 作家・逢坂剛が見た永瀬vs藤井」
永瀬拓矢王座vs藤井聡太七冠、まるで極上のミステリー(逢坂剛) – 日本経済新聞 (nikkei.com)
2019年1月13日 読売新聞オンライン 「最強AI「アルファゼロ」登場で将棋は終わるのか」最強AI「アルファゼロ」登場で将棋は終わるのか : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)
参考文献:
文藝春秋 『文春将棋 読む将棋』 P.40~47