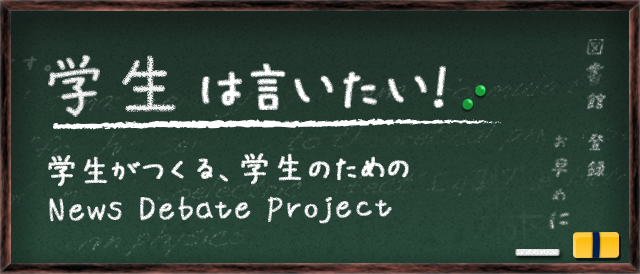新聞記事にはたくさんの情報が詰め込まれている。記事の内容を端的にまとめた「見出し」、視覚で伝える「写真」、活字で表現できることを盛り込んだ「本文」。でも、これだけではない。文末に書かれている「筆者名」も立派な情報だ。
もちろん、知り合いでもない限り、その記者がどんな人なのかは分からない。実名のツイッターアカウントがあればそこから調べられるが、わざわざ一つ一つ確認する読者は多くないだろう。ただ、名前からでも推測できることがある。書き手の性別だ。
今月上旬に行われた参院選。注目すべき点の一つに、当選者に占める女性の割合が衆院選を含めた戦後の国政選挙で初めて3割を超えたことが挙げられる。新聞各紙は、候補者選定のプロセスを取材したり、子育てしながら選挙活動をする難しさなどを報じたりした。
一連の報道記事を読みながら気づいたことがある。それは、女性記者による記事が極めて多いことだ。参院選の女性候補について熱心に報道していた朝日新聞の場合、6月1日から今日までの19本の記事に28人の記者が携わり、うち女性が16人を占めた。ちなみに今日の朝日新聞朝刊に掲載されていた、スポーツ面以外のすべての記事の記者の性別を調べると、男性と女性の比はおおよそ3:1だった。政界の女性に関する記事ではいかに女性記者が起用されたかが分かるだろう。
ここで一つの疑問が湧いてくる。女性という性別にフォーカスした記事は、女性記者が書くべきか、性別にとらわれずに書くべきか。
女性記者が書くことのメリットはかなりたくさんあるだろう。例えば、子育てしながら職場でも活躍する女性を取材する際、既に妊娠、出産をしたことのある記者は自らも「当事者」なので、取材相手の心境に思いをはせやすいと思う。また、生理や更年期障害など女性特有の事情が絡んでくる場合、取材相手が話しやすい雰囲気を作れるのは間違いない。
では、こういった取材は、女性記者だけに任せればいいのだろうか。それは少し違う気がする。私は以前、twitterでこんなツイートを見つけた。朝日新聞コンテンツ編成本部の太田泉生さんのコメントだ。ちょっと女性というテーマから外れてしまうが、みなさんに読んでいただきたい。
” 例えば、不登校を経験した記者が、そうではない記者よりも不登校について深く理解していい記事を描けるかというとそういうことではない。経験した者だからわかるということなら、経験していないことはわからないことになる。当事者と非当事者(社会)をつなぐことこそ仕事だと。”(原文のまま)
斬新な視点だと思う。私は取材経験において太田さんの足元にも及ばないので偉そうなことは言えないが、確かにそのような気がしている。あらたにすの記事を書く際、現場で当事者の声を聞きつつも、いざ執筆の段階ではその問題に関心を持っていない読み手も頭に浮かべながら、どういう書き方・結論がいいか、当事者の声と非当事者の感覚を擦り合わせる。
あらたにすにこれまで書かれた記事の中で、女性という性別に焦点を当てたものの執筆者を見ると、女性メンバーの名前が目立つ。私はこれまでそこに違和感は感じていなかった。でも、男性である自分だからこその視点がもしかしたらあるのかもしれない。また、非当事者が書けば、その社会問題の客観的な評価が伝わりやすくなるという強みもあるのではないか。私だから書けることとは何か、原点に戻って考えてみようと思う。
※ 本文中では女性を「当事者」と表現しましたが、女性が活躍できる社会にするためには性別問わず多くの人の賛同・協力が不可欠だと筆者は考えており、女性以外の性別の人が当該問題の解決において蚊帳の外ということを意味しているわけではありません。また、女性が活躍できる社会は女性以外にとってもプラスであることが多く、男性なども見方によっては「当事者」だと思っております。
参考記事:
朝日新聞デジタル 7月14日「(社説)女性当選最多 『均等』へ さらに努力を」
「政治の世界、知ることから 演説や選挙戦略、講座で学ぶ」「『男の祭り』の選挙変えたくて 『男47・女1』熊本からの挑戦」「子連れ街頭演説、違法?『18歳未満、選挙運動は禁止』」「(Think Gender)国会議員の『男女平等』まだ遠く 政治分野は146ヵ国中139位」など、6月1日から7月26日までの朝日新聞デジタルに掲載されていた政界での女性に関する記事19本
26日付 朝日新聞朝刊(福岡版)
参考文献: