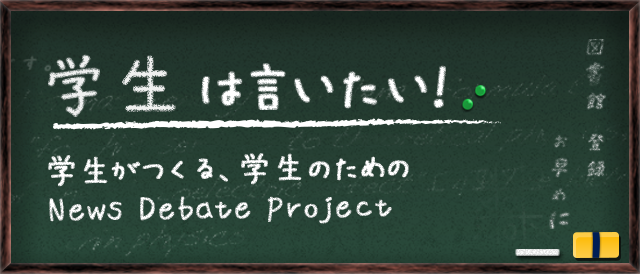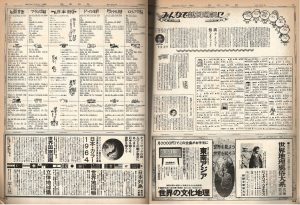その日の東京は秋晴れだった。NHKのアナウンサーは「世界中の青空を東京に持ってきたようなすばらしい秋日和です」という有名な言葉を残している。当時の記録にも「青空」や「秋晴れ」という単語が多くみられる。それもそのはず、57年前の東京は大気汚染がひどかった。開会式の前日の大雨がなかったら空気中の塵が洗い流されず、ここまで澄むことはなかったと言われている。
ただ、この青空は人々の五輪に対する期待感も映し出していたのかもしれない。1964年大会に当時の日本人はどんな思いで臨んだのか、半世紀余りタイムスリップして考察してみたい。
2021年大会が東日本大震災からの復興五輪なのに対し、1964年大会のテーマは戦争からの復興の他に平和や国際協調と言うことができるだろう。ギリシャから聖火をつなぐ聖火リレーは日本軍が戦場とした国々をあえて通るルートに設定された。開会式のわずか9日前に開業した東海道新幹線は、旧陸海軍の技術者が開発に携わった。戦時中は特攻機の設計を担当し、戦後は新幹線の先頭車両を担当した三木忠直氏は「技術は本来的に人間を幸せにするものだ。絶対にそうでなくてはならない」と述べている。
小説家の杉本苑子は開会式当日の共同通信の配信記事で次のような言葉を残している。
二十年前のやはり十月、同じ競技場に私はいた。女子学生のひとりであった。出征してゆく学徒兵たちを秋雨のグラウンドに立って見送ったのである。(中略)暗鬱な雨雲がその上をおおい足元は一面のぬかるみだった。私たちは泣きながら行く人々の行進に添って走った。
敗戦から19年しか経っていない当時の日本人にとって、五輪をめぐる出来事の多くが戦争と切り離すことができず、随所で暗い過去と照らし合わせていた。
また、当時を語る上で、外国人に対する態度も特筆すべき点である。10月12日の読売新聞朝刊には、「外国人に親身に接しよう」というタイトルの読者からの投書が掲載されている。同月1日の紙面の「みんなで親切通訳に」という題名の下には、外国語での会話表現がずらりと並べられていた。
まるでNHKの語学講座のテキストのようである。ここには東京外語大学長の「たどたどしくても誠心誠意をもって話す方がはるかに国際親善に役に立つことを銘記すべきである」という言葉が添えられている。
先ほどの投書にしても、この「語学講座紙面」にしても、当時の人々が外国人と友好関係を築くことに強い関心があったことがうかがえる。しかし、43年10月、東條英機首相は学徒出陣に際して「敵英米を撃滅せよ」と激励していた。たった21年でこの変わりようである。戦争を経験した人が社会の大半を占め、その教訓が社会の規範を作っていた時代と言えるかもしれない。
開会式翌日の10月11日、読売新聞朝刊には後に都知事になる作家石原慎太郎氏の興味深い言葉が掲載されている。それは「人間自身の祭典」という題で始まる。
オリンピックにあるものは、国家や民族や政治、思想のドラマではなく、ただ、人間の劇でしかない。その劇から我々が悟らなくてはならぬ真理は、人間は代償なき闘いのみにこそ争うべきであり、それのみが人間の闘いである。
国家総動員法のもと、国家によって個人が利用されたかつての反省がここに表れていると言えるだろう。
また、現状を振り返ってみると、オリンピックが政治と切り離されているとは言い難い。36年のベルリン大会や80年のモスクワ大会、84年のロサンゼルス大会が国威発揚や冷戦対立に利用されたことは有名な話である。64年の東京大会も北朝鮮などが政治的理由によりボイコットし、朝日新聞は社説で強く非難している。このようにオリンピックは国家が政治的に利用できてしまう祭典でもある。もちろんやり方によっては国際協調をアピールできるが、戦後19年の日本にとってそれは一つの挑戦であったのかもしれない。そのような緊張感を石原氏の言葉から感じる。
私は、今回の東京大会が東日本大震災からの復興五輪だと最初に聞いた時、あまり違和感はなかった。もちろん、今なお福島には帰還困難区域があり、津波の被害が大きかった街には人がなかなか戻って来ていない。復興と断言することには疑問があったが、五輪大会のテーマなんてそんなもんだろうと思っていた。政治的イデオロギーも絡んでくるし、半ばこじつけのようになってしまう性質なんだろうと。しかし、前回の東京大会では平和五輪の要素が随所に表れていたということを知り、その一貫性に多少の感動を覚えるにつれ、今回の「復興」というテーマがあまりにも空虚なものに思えてきた。大会期間中に予定されていた福島の農作物の安全性を海外の人に知ってもらう催しは中止となり、復興というコンセプトだけが虚しく残る。今日の開会式は、この思いを絡めたものといえるのだろうか。
もちろん、オリンピックの本来の目的との親和性は重要な要素である。前回の東京大会が掲げた平和というテーマは、近代オリンピックの「平和でよりよい世界の実現に貢献する」という理念に符合する。一方、今回の震災復興は理念とは一定の距離が感じられる。だとするならば、テーマを設ける必要がどこまであるのかということは考えなければならない。
政府は以前、復興五輪と声高に言ってきたが、最近はそれに触れなくなった。コロナが流行してからは「人類がコロナに打ち勝った証」と位置付けたが、それもあまり聞かなくなった。
もう何かプラスαにこだわる必要はないのではないか。コロナで人の往来が減り、各国が閉鎖的になっている今日においては、オリンピックの基本理念を確認するだけでも十分意義があると思う。
22日、茨城県のカシマスタジアムではサッカー男子の試合が行われ、地元の学校の生徒だけが観戦した。それに先立ち、ニュージーランドの応援をすることになった波野小学校の生徒は手作りの応援旗を作り、裏面には英語で「Let’s go!」といった応援メッセージを書き込んだ。日本人がこのようにわざわざ他国の応援の準備をすることは珍しい。生徒以外に客の姿はなく、完全にアウェーな状態で闘う外国人選手を配慮したものかもしれないが、国際協調に大きく寄与していることは間違いない。コロナ禍による無観客というマイナスをうまく活用した取り組みであり、他の国の選手の応援に対しても同様の取り組みがあるとなお良いと思う。
近代オリンピックの父、グーベルタンは「オリンピックで重要なことは、勝つことではなく、参加することである」と言い残している。感染対策を理由に参加を見送る国が出ている今大会では既に理念に反している部分があり、そこまでしてどんな意義があるのかという批判はある。ただ、制限が大きい今大会でも、先の例のように五輪の理念に即した取り組みは限定的ながらも可能である。
19時50分、NHKでは開会式直前SPが続いていた。紅白の前のような妙な緊張感。どんな開会式、どんな大会になるのだろう。このオリンピックが単なる「お祭り」に終わることなく、国際協調や平和に寄与するものになってほしいと強く願う。
参考記事:
1964年10月1日付 読売新聞44・45面「みんなで親切通訳に」
同年10月10日付 朝日新聞2面「社説 オリンピックの開会を迎えて」
同年10月11日付 読売新聞17面「オリンピック断章 人間自身の祝典」
同年10月12日付 読売新聞2面「外国人に親身に接しよう」
参考資料:
映像の世紀プレミアム(15)「東京 夢と幻想の1964年」、NHK 、 2021年7月22日放送
NHK NEWS WEB「五輪 カシマスタジアムで観戦の小学生 応援の旗作り」