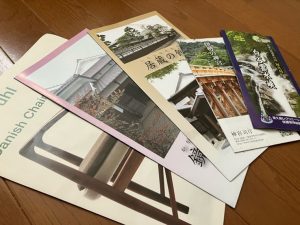23日の読売新聞に伝統芸能の案内人へのインタビューが掲載されていました。歌舞伎や文楽で見どころや演者の情報を伝えるイヤホンガイドをする高木秀樹さん、外国人のための文楽鑑賞教室でナビゲーターを務めるクリス・グレンさん、上演前や幕間に案内役を務める葛西聖司さんの3人です。彼らは歌舞伎や文楽などの魅力を伝え、お客さんがより楽しめる工夫をしていますが、実は「ガイド」はいろいろなところにいます。
例えば観光地。旅行先では現地の地図や観光案内といった資料を必ずもらってじっくりと目を通します。初めて訪れる場所は行く前におすすめ場所やご飯屋さんを調べますが、やはりパンフレットの力はすごいものです。自分で歩いて、どのようなところかを知り、ふらっと行きたいところに入る、それが穴場だったらなお嬉しい、というのも楽しみ方の1つですが、せっかくなら先人の感覚を信じようじゃないか。限られた時間で巡る際に、これほど頼れるものはありません。
筆者は三重県の伊勢神宮に行った際も、まずはパンフレットをもらいました。友人とポイントを逃さぬよう真剣にまわります。もう二度とこないかもしれないと思うと、すべてまわり尽くしたくなってしまうものです。
さて、これで満足だと思ったところで、ガイドさんと出会いました。「お伊勢さんの観光案内人」のおじさんです。たまたま他の方の案内役を終えて帰るところで遭遇し、パンフレットを真剣に眺めていた私たちに声をかけてくれたのです。案内書の活字とは異なる、肉声で魅力を伝えてくれました。伊勢神宮にまつわる神話や直近のイベント、どのような時期がおすすめか、お伊勢さんまいりの順番やその理由などあふれんばかりの情報です。
気になる!と目を輝かせると話をさらに深掘りしてくれます。今まで何気なく使っていた、神宮、大社、宮の違いも教えてくれ、新たな発見がたくさん。それも一方的な案内ではなく、会話テンポで説明を聞けることが魅力です。伊勢神宮にまつわる話はなんでも教えてくれる、まるで歩く事典です。「意外と面白いでしょ?」とおじさん。旅行者が楽しんでくれることを日々実感しているからこその言葉でした。
美術館や博物館にもよく行きます。パンフレットはもちろんのこと、作品の横にある小さな説明書きも真剣に目を通します。もちろん、感覚だけでみてまわることもありますが、いつ描かれてどういう背景なのか、なにが影響しているのか、どうしても気になってしまうのです。絵画であれば、製作年、キャンバスの種類、画材など基本的な情報が書かれており、さらに、同じ作品が来ていても、展覧会ごとに作品から受ける印象が変わるなど、展示の構成からもさらなる情報を得ることができます。さまざまなところに「ガイド」は散らばっているのです。
他にも山歩きの案内人、美術館の音声モニター、展示をまとめた図録、そして一緒に行く詳しい友人など、「ガイド」の種類はさまざまです。せっかく行くなら、ちょっとの工夫でより深く知るチャンスに巡り会えるのです。
参考記事:
23日付 読売新聞朝刊(福岡12版)23面文化「ガイドの流儀」