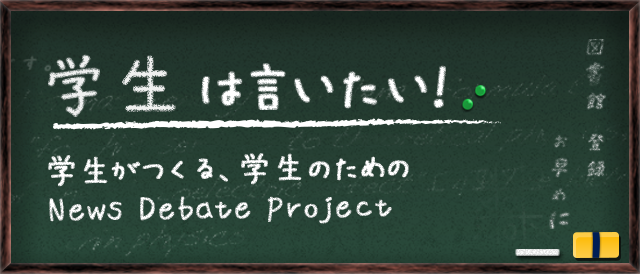記憶は雪のふるやうなもので しづかに生活の過去につもるうれしさ
今日が忌日の萩原朔太郎による詩の一節です。今朝の読売新聞「編集手帳」では、この言葉を引き合いに「記憶は“つもる”もの」だと論じています。
しかし、一方で、記憶は風化するものでもあります。どんなに悲惨な歴史も、時間とともに忘れ去られてしまう。あるいは、積もっても嬉しくないような、忘れてしまいたい辛い記憶もあるでしょう。
被爆三世とその家族の撮影を続ける女性がいます。広島で生まれ育った堂畝紘子さんです。プロのカメラマンとして戦跡を撮りながら、何が伝えられるのか悩んでいました。写真を撮るきっかけとなったのは、友人である被爆三世からの「私と家族を撮らない?」という提案。広島・長崎から募集した被写体の家族は、70組にものぼります。
現在、彼女の写真展「生きて、繋いで-被爆三世の家族写真-」が都内で開催されています。
東京汐留で開かれている写真展(入場無料、30日まで)
写真の下には、被爆体験が日本語と英語で添えられていました。撮影時に、被写体である三世が、おじいちゃんやおばあちゃんから直接伝え聞いたものです。中には、「今日がなかったら祖母に一生話を聞けなかった。」と感謝する大学生や、「話せてよかった」と言う被爆者もいるそうです。
社会に記憶を残すだけでなく、家族のライフヒストリーを共有する機会としての役割も果たしています。戦争体験を語る「語り部」の研修を受けている私にとって、とても考えさせられる展示でした。
高校生のとき、被爆者の方に言われた言葉が今でも忘れられません。
君たちは、実際に戦争を体験した人から直接話を聞ける、最後の世代だ。だから、聞いたことをきちんと伝えていってほしい。
しかし、それも厳しい時期に差しかかっています。体験者の高齢化が刻々と進んでいるからです。生存していても、他人に話をできるような状態でない方も増えています。
戦後、被爆者に対して差別の目はひどく、何十年も被爆を隠していたという人は少なくありませんでした。それでも、封印していた記憶を呼び覚まし、閉ざしていた口を開いて懸命に伝えようとした体験者たち。社会は、その思いを真摯に受けとめることができているでしょうか。
誰でも、戦争体験者が家族や親戚にいたはず。決して他人ごとではないのです。
これから戦争の記憶を風化させずに“つもらせる” のは、戦後生まれの私たちなのだと思います。
参考:
11日付 読売新聞朝刊(東京14版)1面「編集手帳」
同日付 朝日新聞朝刊(東京14版)15面(東京)「被爆3世 平和継ぐ家族写真」