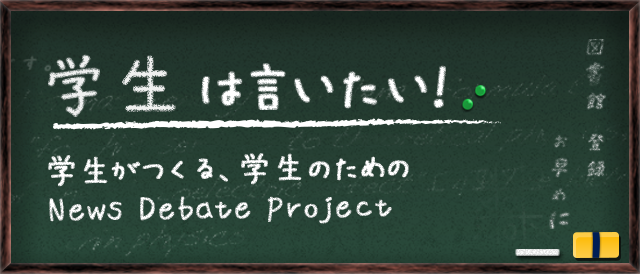普段の生活の中では忘れていますが、20歳になると一部の専門家を除き、誰でも選ばれる可能性がある制度をご存知ですか。それは「裁判員制度」です。今ではだいぶん認知されましたが、いざ選ばれるとなるとその負担はとても大きいものだと言われています。
本日の新聞では、裁判員を務めた女性が、証拠として挙がった被害者の遺体の写真を見せられたなどして、急性ストレス障害になったとして国に損害賠償を求めた訴訟を取り上げています。最高裁は、女性の訴えを棄却した仙台高裁の判決を確定させ、女性の訴えを退けることになりました。
今までの裁判では、すべての刑事事件において検察や弁護士、裁判官といった専門家によって行われていました。出てきた証拠について討論し、被告人にかけられている容疑が、「疑う余地のない」場合にのみ罰せられます。
その、専門家によって行われていた裁判を変え、裁判員制度を導入した目的の1つには、裁判の判決に民意を反映することが挙げられます。「なんであんなにひどかった事件だったのにこんなに罪が軽いのか?」といったようなことが増えてしまうと、それだけで裁判所に対しての不信感を抱かせてしまうことになります。そのため、一部の事件については、無作為に選んだ国民を「裁判員」にすることによって、裁判に国民の意見を取り入れようとしているのです。ただ、慣れていない「素人」を裁判に混ぜることは、かかわるすべての人にリスクがあります。
まずは、裁判員に選ばれてしまった人です。裁判によって、長時間拘束されるだけでなく、普段なれない法律を扱い、先ほどの記事のような、見たくもない写真や証拠と向き合わなければいけません。
裁判員に選ばれていない国民にもリスクがついてきます。刑事裁判は「疑わしきは罰せず」といったものや、ある犯罪に相当する以上の罰を与えてはいけない、といったルールがあります。このようなルールはすべて、国民のために作られたものです。裁判員裁判で「死刑」判決を受けた事件はいずれも高裁で「無期懲役」になるなど、専門家の目から見ると重過ぎると判断することが多くあります。
裁判員を務めた女性による訴訟は、裁判に一般人を混ぜることのむずかしさを改めて浮き彫りにしました。一方で、大学で普段法律を学んでいると、はてなマークが浮かんでくるような裁判例はいくつもあります。このようなギャップを埋めていくためにも、今のような裁判員裁判を定着させるのではなく、最小限度にとどめる必要があるのではないでしょうか。
参考記事:
28日付:東京14版 朝日新聞 朝刊3面「「裁判でストレス」敗訴確定」