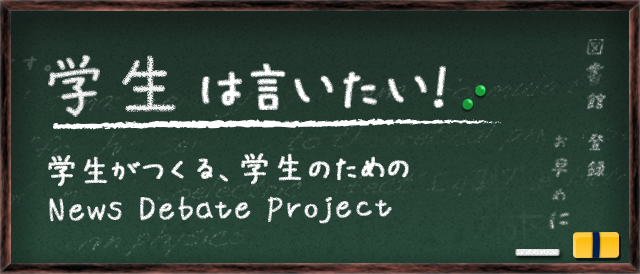私の地元は、田んぼや川、山に囲まれた自然豊かな場所でした。春には白つめくさで花冠を作り、梅雨にはカエルの合唱を聞き、夏には用水路でザリガニを捕まえ、秋にはトンボを追いかけていました。田植え体験やカカシ作りも地域の恒例行事で、稲の間を飛び交うスズメの姿は日常の風景でした。中学生の頃には、下校中にその鳴き声をBGMのように聞いていた記憶があります。
しかし近年、地元の再開発が急速に進みました。田んぼは次々と潰され、新しい住宅や商業施設が建ち並びました。気がつけば、あれほど身近だったカエルやザリガニの姿は見えなくなり、スズメの声もほとんど聞こえなくなってしまいました。変わってしまった地元の風景に寂しさを感じる一方で、それが「自然な変化」ではないと気づいたのは、ある新聞記事を読んだときでした。
日経電子版の19日付「日本列島から鳥・虫が激減 暑くなりやすい国土も影響か」には、私が地元で感じていた違和感の正体が記されていました。記事によれば、2005〜22年度にかけて、日本の里地・里山にいる鳥類の15%、チョウ類の33%が減少したということです。かつてはどこにでもいたスズメやイチモンジセセリまでもが、環境省のレッドリストに載るほどだというのです。私が感じていた「スズメの声が消えた」体験は、単なる個人の感覚ではなく、日本全体で起きている変化の一部だったのだと知りました。
その原因の一つとして挙げられているのが、気候変動です。気温の上昇は、生き物に直接的なストレスを与えるだけでなく、生態系のバランスを壊しています。実際、日本は気温上昇の速度が世界平均よりも早く、100年あたり約1.4度のペースで上昇していると、環境省と気象庁は報告しています。
さらに、農薬による生態系への影響も見過ごせません。私は農薬が虫に悪い影響を与えることは知っていましたが、日経の記事を読むまで、ミツバチや他の生物の免疫にまで影響を与えて病気を引き起こす可能性があるとは知りませんでした。農薬の中でもネオニコチノイド系と呼ばれる殺虫剤は、水田や都市部を問わず広く使用されており、ミツバチをはじめとする昆虫や、それを捕食する鳥類にまで影響が及んでいるということです。農薬が生態系の複雑なつながりを断ち切っている現状に、改めて危機感を覚えました。
私は、再開発によって田んぼや川が失われていく現状を、決して「仕方のないこと」だとは思っていません。むしろ、長年そこに存在していた貴重な自然が急速に奪われていくことに、強い違和感と恐怖を感じています。カエルの鳴き声も、スズメのさえずりも、ザリガニを探して歩いたあぜ道も、私にとってはただの風景ではなく、自然と共にある暮らしの一部でした。
自然と共にあった風景が失われつつある今、私たちは何を選択し、どんな未来を描くべきなのでしょうか。目の前の変化を受け入れるだけでなく、農薬の使用や土地開発のあり方、そして気候変動への取り組みを見直すことが求められています。日々の小さな意識や行動が、これからの社会や環境をかたちづくっていくのだと思います。
参考記事:
19日付 日経新聞デジタル「日本列島から鳥・虫が激減 暑くなりやすい国土も影響か」