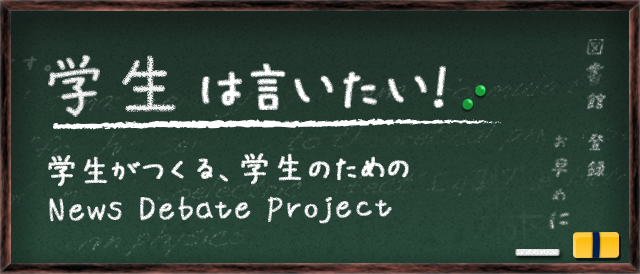前回では、「世界でも珍しい」とされる国民審査制度の全体像を紹介しました。では、なぜこの制度が導入されたのかでしょうか。このことは、あまり知られていません。同制度が憲法79条に規定されていることからもわかるように、戦後の憲法制定までさかのぼって考える必要があるでしょう。
1946年2月3日、日本側の憲法草案が保守的だとして、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)のマッカーサー最高司令官は、天皇の地位や戦争の放棄を提唱した「マッカーサー三原則」を日本政府に提示しました。そして、翌4日には、GHQ民政局において憲法草案の作成作業が開始されます。
司法制度を検討したのは「司法権に関する委員会」で、M.E.ラウエル中佐、M.ストーン、A.R.ハッシー海軍中佐の3名で構成されました。同委員会の第一次試案では、司法権の独立に重きが置かれ、裁判官の終身制などを盛り込みました。ただ、この試案について草案全体を調整する「運営委員会」のケーディス陸軍大佐は、司法の権力が強すぎるのではないかと懸念を示しました。
結局、両者の妥協で下級裁判官については10年の任期後、再任を妨げないとしました。そして、最高裁の裁判官について、
「最高裁判所は、首席裁判官および国会の定める員数の陪席裁判官で構成される。これらの裁判官は、すべて内閣によって任命され、非行のない限り65歳に達するまでその任にあるものとする。ただし各現任者は、任命後最初の総選挙の際およびその後10年ごとに、選挙民がその者をその地位に留めるか否かを決定するための審査に付される」
と第二次試案の58条に規定されました。ここで初めて「国民審査」の制度が試案に登場することになります。
やや唐突な印象を受けるこの制度は、一体どこから来たのでしょうか。アメリカ法曹協会の勧告やカリフォルニア州での立法例を参考にしたとラウエル中佐が後年インタビューに答えています。このことから、当時のアメリカにおける司法をめぐる議論が日本の国民審査制度の誕生に影響を与えたものとされています。
当時のアメリカは、第7代ジャクソン大統領の民主的な政策の推進(「ジャクソニアン・デモクラシー」)などにより、裁判官の公選制が導入されていました。しかし、選挙で裁判官を選ぶと政治的な色彩を帯びてしまうとの批判を受け、さまざまな修正がなされました。
その一つが、国民審査制度のように裁判官を有権者がチェックする制度です。州知事が裁判官を任命した後に州民が審査を行うことで、党派性が排除できると考えられました。同制度はミズーリ州で初めて導入され、その後カリフォルニア州でも導入されました。憲法制定の時点では、両州のみがこの州民審査を実施していたようです。
このように、GHQにおける10日間の作業で作成された草案が、2月13日「マッカーサー草案」として日本政府に示されました。これを元に「憲法改正草案」が作成され、新憲法の最終的な策定は日本政府に委ねられることになったのです。
6月20日、「帝国憲法改正案」として帝国議会で発議されました。この時点でも国民審査制度は草案の形で残っていましたが、9月に入り高柳賢三・東大教授などが反対論を唱えました。帝国憲法改正案特別委員小委員会で同氏は、判例などは国民に容易にわかるものではないとして、国民審査に批判的な意見を述べました。
こうした反対論を受け、10月2日、国民審査に関する条項の廃止を小委員会に諮ったところ、満場一致の賛同が得られて廃止が決定。そのまま3日に帝国憲法改正案特別委員会へ送られました。しかし、一転して特別委員会では同案が否決され、国民審査制度は息を吹き返しました。
この1日の間に何が起きたのでしょうか。3日、GHQのホイットニー民政局長は、国民審査の削除に関して「政府は十分な配慮」をすることとする申し入れを行いました。事実上、GHQが国民審査廃止に対してけん制したものとみられています。こうした帝国議会での紆余曲折を経て、同制度は現行憲法に盛り込まれることとなりました。
資料を読む限り、議会やその他の機関で国民審査に関してそれほど多くの議論があったようには見えません。当時は、天皇の地位など多くの重要論点があったためでしょう。ただ、同性婚の問題など司法の決定が国民の生活に直結することも多い昨今、改めて私たちの目指すべき司法制度とは何か考える必要があるでしょう。
<参考文献>
梅川健「2018年中間選挙とアメリカの州裁判官公選・審査制(1)」
西川伸一「最高裁裁判官国民審査制度はどのようにしてつくられたのか」
田中英夫『アメリカの社会と法: 印象記的スケッチ』東京大学出版会、1972年。
西川伸一「最高裁裁判官国民審査の実証的研究「もうひとつの参政権」の復権をめざして」五月書房、2012年。