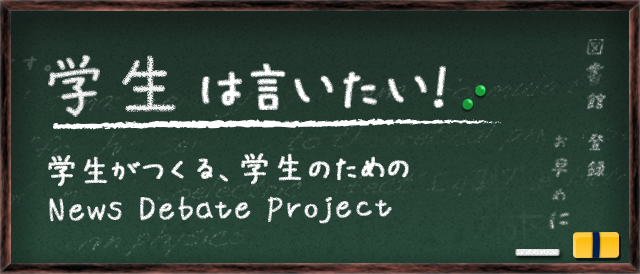先月28日に投稿した記事の執筆で宇治茶について更に詳しくなりたいと強く思うようになりました。そこで毎年開催されているという「宇治茶ムリエ講座」に参加してきました。
この講座では、1時間という短時間の中でお茶の歴史や種類、淹れ方を学ぶことが出来ます。受講者の規模も20人程度と少数のため、より丁寧かつ綿密に教えてくれました。特に宇治茶の淹れ方実習では、日本茶インストラクター協会から派遣された講師からどこよりも分かりやすく指導してもらい、楽しんでお茶を学ぶことが出来ました。
ここでは、お茶の淹れ方に焦点を当てていきます。美味しいお茶を淹れるには、湯温・湯量・茶葉の量・お湯を急須に入れてからの時間が大切です。お湯は、ヤカンの蓋を開けて3-5分間しっかりと沸騰させます。そうするとカルキ臭が抜け、余分な空気を放出させるといいます。
1杯目の茶は40-60℃ほどに冷ました湯で淹れると、より甘さが際立ちます。また、2杯目以降は1杯目よりも熱い湯でより深みのある茶を楽しむことが出来ます。
京都府宇治茶普及促進条例なるものが平成31(2019)年から施行されていたことを知りました。これは、宇治茶の伝統や文化を守り更なる発展に寄与するためのものです。府民の役割として、以下が挙げられています。
「第3条 府民は、自主性に基づき、日常生活において、宇治茶に親しみ、宇治茶の伝統と文化等に触れることを通じて、宇治茶や宇治茶の伝統と文化等に関する関心と理解を深めるよう努めるものとする。
2 府民は、府及び市町村並びに茶業者等が行う宇治茶の普及の促進等に関する取組に協力するよう努めるものとする。」
今回の宇治茶ムリエ講座に参加した50代女性は、「外国でも抹茶やお茶はブームだと聞きますが、外国流にアレンジされてしまうので、日本人が頑張ってきちんと基本を押さえて知っておかなければ!とつくづく思う今日この頃です。基本を知った上で崩すようにしないと」と話します。
受講後は、「宇治茶ムリエ」の認定証が渡されます。この認定証を頂いたおかげで、知人に宇治茶を紹介したい衝動に駆られます。私を含めた宇治茶ムリエが、宇治茶の伝統や文化を担う一端を背負っていけたらと思います。是非みなさんもお茶に触れ、その奥深さを味わってみてください。
参考記事
2024年5月1日付 日本経済新聞「京都・宇治、八十八夜の新芽摘み 新茶シーズンが到来」.
2024年5月28日付 あらたにす「世代や歴史を超えて愛される宇治茶を目指して」.