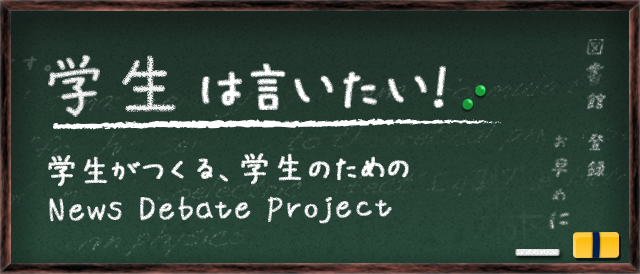最近、『うたわない女はいない』という本を読んでいる。「働く女性」をテーマにした短歌とエッセイを収録している。
この本でも「働く」ということにフォーカスを当てているように、「労働」と歌は関係が深いと感じる。短歌では、労働というテーマ設定はよく見られるし、音楽ジャンルの一つであるブルースは、昔から歌い継がれてきた労働歌から発展したものと言われている。
なぜ労働を歌にしたくなるのだろうか。日本で「歌を詠む」を言えば、俵万智の「サラダ記念日」のような現代詩ではなく、小倉百人一首に登場するような平安貴族の詠んだ短歌を思い浮かべる人が多いだろう。しかし、平安貴族のいとをかしな歌の中では、あまり「働く」ということに焦点を当てたものはない。阿倍仲麻呂の「天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも」(遣唐使として中国に渡った作者が日本への郷愁を詠んだ歌)のようなものも確かにあるが、どちらかというと自然や故郷などといったものへの趣深さに、より主眼が置かれているのではないか。
そもそも昔の短歌というのは、社会的地位が高く、教養のある貴族のたしなみであった。逆に身分が低く、学がないとされたものには到底詠むことはできないと考えられていただろう。だが、現代では違う。どんな身分でも歌を作ることはできるし、労働者だからこその日常の哀愁や、まなざしを歌の中に詠み込むことが粋になる。逆に使用者、資本家の歌というのは、探せばあるのかもしれないが、見たことがない。億万長者の短歌があれば読んでみたいものだが、そこには哀愁や私たちが共感するような身近な目線はどれくらいあるのだろうか。それとも、資本主義では、忙しくて歌を詠む暇なんてない、ということだろうか。いずれにしても平安時代から現代にかけ、文化の裾野が広がるにつれて、文化の担い手が上から下に逆転したと言えるのかもしれない。
ただ、より時代を遡ってみると、「万葉集」では、天皇の歌から東歌まで、様々な人の歌が収録されている。諸説あるが「万葉」とは「万の言の葉」の意味があり、多くの歌を集めたものとしてひとつ解釈することができるだろう。その中でも、九州沿岸の守る防人による歌も多く選集されている。防人歌が収集される背景には、防人制度が揺らぎ始めた奈良時代中期に、防人の情報収集の一環として行われた可能性があるという指摘があるが、厳しい環境を強いられた防人たちにとっては、自分の苦しい状況を歌として形にしないではいられなかったのだろうか。防人歌はプロレタリア文学的な要素を持っていたと言えるかもしれない。
『うたわない女はいない』の中では、三十六歌仙にちなんで36人の女性がそれぞれの日常を、おのおのの感性で詠んでいる。働くことが性に合っているんだなと思わないではいられない詠み手もいれば、「働く」ということに対して、ある種の諦めを持っている人もいる。でも、どちらも歌になる。
一ヵ月とすこしすれば、私も社会人になる。アルバイトはしたことがあるとはいえ、学生の肩書がなくなって、新しい環境に踏み出す。どのように感じるかはまだ分からない。ただ、どうあろうとも歌を詠めるくらいの余裕を持って、新生活に臨みたい。