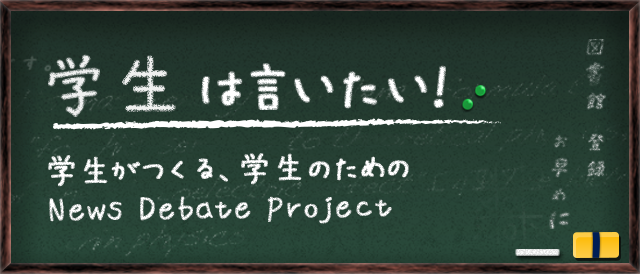コロナ禍の閉塞感が漂う中、東京オリンピック2020が開幕しました。皆さん、それぞれの眼差しで開会式を迎えたと思います。高揚感、失望感、不安、無関心。どんな気持ちでしたか?
筆者は、本音を言うと「もう、どうでもいい」でした。アスリートの活躍を願う一方で、競技の結果以上に観光客との交流に興味があったのです。今回は民間レベルの国際交流は不可能なため、日本の「おもてなし」を発信する場が失われたと感じました。失望感はかなりのものです。筆者は懐石料理店に勤め、日々お客様への心遣い、日本の文化に触れています。オリンピック招致の際にアピールした「おもてなし」を市民レベルで発揮できれば、この大会がより盛り上がると確信していました。だからこそ、「今回のオリンピックは、なかったようなものだ」。このような極論に至ってしまったのです。
無力感にとらわれた筆者に、ある記事が気づきを与えてくれました。24日付の読売新聞朝刊に掲載された牛久保さんへのインタビューです。彼は国立競技場前のラーメン屋の店主であり、観光客への期待を膨らませていたうちの一人です。牛久保さんは、「緑でおもてなしをしよう」と数年前から木を植えていたと言います。券売機の横の多言語看板も目を引きます。海外観光客が押し掛けてくるのを見越して、常連さんが作ってくれたものです。オリンピックに向けて数々の準備をしてきましたが、コロナ禍で一変しました。観光客との交流を制限され、複雑な思いも抱えたようです。しかし、牛久保さんはこう語ります。「精一杯おもてなししたい気持ちは変わらない」。五輪が終わっても国立競技場は五輪遺産として残り、千駄ヶ谷は競技場の町として営みが続いていく。選手の乗るバスには笑顔で手を振るつもりだそうです。いつかコロナが収束した際、また再訪してほしいという願いを込めて。
記事を読んだ際、自分の考えが浅はかだったと気づきました。開催期間だけに焦点を当てていましたが、「今」は思う存分力を発揮できなくても「未来」を見据えて行動することはできるのです。パラリンピックを含む1ヶ月半に及ぶ大会期間が終わっても、東京でオリンピックが開催された事実は歴史に残ります。感染が終息したら、海外からの観光客が「五輪が開催された場」として来日してくれる可能性は大きいでしょう。その時、我々が大会に向けて準備したおもてなしに触れてもらう機会は作れるはずです。
1964年の大会でも手土産として配布した提灯や扇子の「江戸みやげ」を浴衣で配ったり、和食マップを準備したりと、様々な方法が浮かんできます。可能性は未知数です。競技場の見学を含む無料ツアーを開催しても面白そうです。そうした取り組みは、オリンピックボランティア活躍の場にもなります。このように、準備したものを0にせず、未来の場につなぐこともできるのです。
思えば、過去の大会でもおもてなしの心はその場限りで終わりませんでした。前回の東京大会で発表されたピクトグラムはその象徴です。これは絵の標識を指しており、言葉を使わずに一目で競技や施設を表したものになります。言葉の通じない海外の人々が5万人も来日する。どうしたら彼らが生活しやすいだろうか。文化が違う人々をどうやったらおもてなしできるか、真剣に悩む中で生まれたのです。これはのちに、勝見氏を筆頭に『社会に還元する』といってデザイナーたちが著作権を放棄。世界へと広がり、4年後のメキシコオリンピックにも使用されました。現在も、競技に合わせて様々なアレンジが加えられながら活用されています。今回の五輪開会式での「動くピクトグラム」演出も、『面白い』と国内外から賞賛が送られています。時空を超えて、半世紀以上前のおもてなしの心は生きているのです。
おもてなしはその場限りのものではない
この視点は、今を耐える支えになると感じます。未曾有のコロナ禍で迎えた大会。誰もが思い描いてきた五輪の日々を過ごせていません。私のように「もういいや」、そう思った人も少なくないはずです。特にボランティアを志望した人や観光業を生業にする方は準備をした分、遣る瀬無い気持ちを抱いたと思います。だからこそ、将来オリンピック開催の地を訪問してくれる人々のためにも、腐らずに東京五輪2020を見届けることにします。
参考記事:7月24日 読売新聞オンライン 笑顔で見届けたい おもてなしの心変わらず
参考文献: 読売新聞 1964東京五輪の記憶
NHK 光る各国の個性!オリンピック歴代ピクトグラムを一気見せ