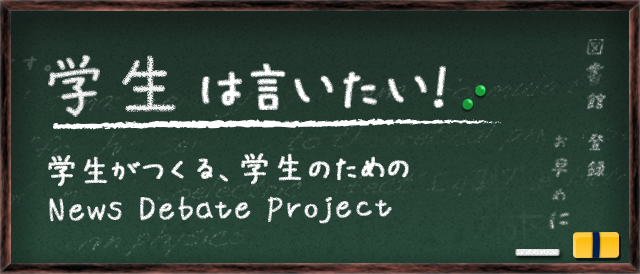15日、新聞週間が始まった。今年は、新聞と権力との距離を考えさせる出来事が多かった。
例えば、賭けマージャン問題。緊急事態宣言が出ている中、黒川弘務・東京高検検事長と朝日新聞社員(元記者)と産経新聞記者2人が賭けマージャンをし、黒川氏の辞任にまで発展した。「報道機関の使命は『権力の監視』というが、実際は権力とべったりじゃないか」。多くの人々がそう思ったのではないだろうか。
報道機関と権力の距離を考える上で重要な人物がいる。ジャーナリスト・徳富蘇峰だ。蘇峰は、月刊誌「国民之友」や「国民新聞」の創刊者で、明治期において、藩閥政治に批判的なジャーナリストの代表格であった。
しかし、蘇峰は反政権から親政権に一気に「変節」していった。そのきっかけとなったのは、日清戦争であった。戦時中、蘇峰は戦況に関する情報を入手するため、知人であった参謀次長に接近し、情報収集をしていた。ここまでは良いだろう。しかし、蘇峰は自分の秘書を参謀本部に送り込んだり、藩閥政治家の意見書の代筆を担当したりするようになるなど、取材には直接関係のないことまで積極的に始めた。
日清戦争での権力との急接近を機に、蘇峰は従来のような政府や藩閥を厳しく批判する姿勢から一転、政府寄りの報道をするようになった。
それを世間に最も印象づけたのは、第二次松方正義内閣の内務省勅任参事官に蘇峰が就任したときであった。松方といえば、薩摩藩出身で藩閥政治家の代表格である。そんな松方内閣への蘇峰の参画は様々な批判を呼び、『藩閥之友』『藩閥新聞』と揶揄された。しかし、権力に取り込まれた蘇峰にとってこのような批判は馬の耳に念仏。『国民新聞』は松方内閣の機関紙と化していった。藩閥批判をモットーとした時代から5年を経ず、『国民新聞』は『御用新聞』に成り果ててしまったのだ。
政治学者の米原謙は蘇峰の「変節」を以下のように評している。
「その一歩一歩はけっして不可解なものではなく、むしろ納得できる理由によるものだった。(中略)だがその変化の積み重ねの結果は、最初の一歩からは想像できない大きな懸隔を生みだした」
これぐらいは取材のうち、そう考えているうちに権力に取り込まれた蘇峰。報道に携わる者は、権力との距離は常に一歩進んでは一歩戻る。そんな慎重な姿勢が必要なのではないだろうか。
蘇峰のようにはなってはならない。
参考記事:
17日付 朝日新聞朝刊(大阪14版)17〜20面「権力とメディアの関係考える」
参考資料:
米原謙『徳富蘇峰 日本ナショナリズムの軌跡』中公新書、2003年