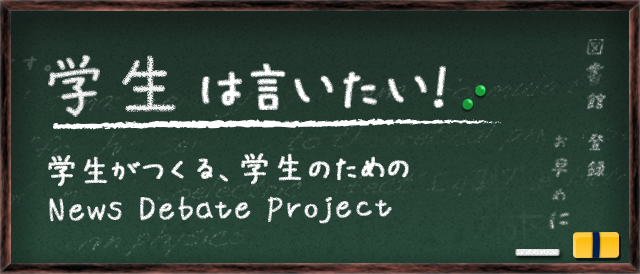昨年12月、私筆者は滋賀県東近江市にある「滋賀県平和祈念館」を訪れました。「語りつぐ平和へのねがい」をコンセプトに掲げ、被害者の「語り」そのものを展示の主役に据えています。戦後80年が経過し、直接の体験者が少なくなっていく中で、私たちはどのように戦争という「記憶」に向き合うべきなのか。同祈念館の取り組みから、その答えを探りました。
「音で語る」生々しさ
この祈念館施設の最大の特徴は、体験者の言葉を生のまま展示している点です。常設展の一部には、「『ばたばた、ばたばた』死んでいきましたわ」や「死体がろうそくみたいにカラカラカラカラと落ちていきよる」といった残酷な言葉が、当時の語り口そのままに展示されています。こうした言葉には、方言や独特の言い回しがを含まれてんでおり、現代の若者や子供たちにとっては、日本語として理解しにくい部分があるのも事実です。しかし祈念館としては変に要約せず、できるだけ生の言葉をそのまま伝える展示することにこだわっています。リアルの言葉で届けることこそが、当時の現場を映し出す何よりの証拠になるからですります。
滋賀県が語る戦争の価値
四年前から職員として働く田井中洋介さんは、この祈念館の立ち位置の難しさを語ってくださいましたいます。「滋賀県は広島や長崎のように、一瞬で都市が壊滅するような甚大な被害を受けたわけではありません。だからこそ、伝え方の難しさがあるのです」。広島や沖縄のような象徴的な場所ではない中で、いかに戦争を語るか。「伝えたいのは、そんな滋賀県であっても、戦争の被害はこれほどまでに深く、広範に及んでいたということです。特別な場所だけでなく、日本のあらゆる場所で、戦争が人々の当たり前の生活を壊していたことを知ってほしいのです」。
入口付近には、当時の県内各市町の人口と戦死者数が掲示されています。身近な町の具体的な数字を見ることで、戦争は一気に「自分事」として迫ってきます。また、展示は戦地の兵士だけでなく、残された妻や、配給の少なさに飢えた人々女性たちの苦悩にも光を当てます。「戦争の全体像は戦地だけでは表現できない」という言葉の重みが数々の展示から重く伝わります。
未来につなぐ「記憶」の形
現在、来館者の中心は平和学習で訪れる小学6年生です。田井中さんは「80年前に自分の住む町でこんなことが起こっていたことを身近に感じてほしい。小学生だけでなく、より多くの人に平和について関心を持ってもらえれば」と話します。また、今でも祈念館には毎週のように遺品や資料をの寄贈する相談が絶えないといいます。しかし、物理的なスペースには限りがあります。デジタルアーカイブ化も進めていますが、膨大な資料のどれこを展示し、どこまでを受け入れるべきかという判断は、平和を祈る念館の在り方そのものを問う重い課題です。「モノ」ではなく、その背後にある「記憶」をいかに大切に扱い、次世代へ手渡していくか。模索は続いています。
言葉のバトンを受け取る
滋賀県平和祈念館が大切にしているのは、一人の人間が戦争の中で感じた「リアルの声」です。その声に耳を澄ませ、痛みを想像し、語りを大切に受け取ること。それこそが、戦争の記憶が薄れる今、私たちが踏み出すべき継承の第一歩なのではないでしょうか。