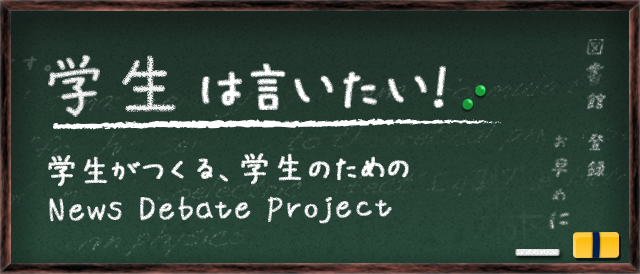長かった夏が終わり、ようやく寒くなってきました。今年、筆者の住む京都では最高気温が35度以上となる猛暑日が60日もあり、例年の比でない暑さは地球温暖化が進行しているせいなのでは?と思わずにはいられませんでした。
10日、ブラジルで第30回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP30)が開幕しました。COPは1995年から開かれていて、今回は各国が国連に提出した2035年の温室効果ガス削減目標を検証するといいます。過去、1997年には「京都議定書」が採択され、先進国に温暖化ガスの削減を義務付けました。2015年には「パリ協定」が採択され、産業革命前からの世界平均気温の上昇を1.5度に抑えるため、途上国にも温暖化ガスの削減を求めました。日経新聞によれば、今回の日本の削減目標は「2035年度時点で13年度比60%、40年度時点で73%」というものだそうです。
温暖化ガスの削減について、「2国間クレジット制度(JCM)」というものがあります。日本が技術や資金を提供して外国の温室効果ガス排出を削減し、その削減量を日本の削減量として扱うというものです。今回、タイで削減された1009トン分は、日本の削減量とみなされました。現地の工業団地に日本と現地企業が協力して水上太陽光パネルを設置し、削減した分だといいます。
このような途上国への援助策がCOP30の焦点になりますが、温室効果ガス排出量が世界2位のアメリカがパリ協定からの離脱を発表したことで難航する恐れもあるそうです。
温室効果ガスの具体的な削減方法として、化石燃料の使用を減らすことが挙げられており、近年はバイオ燃料が注目されています。サトウキビなどの植物から作られるバイオエタノール、廃食用油などから作られるバイオディーゼル、廃食用油や藻などから作られ航空機の燃料となるSAFなどです。
筆者が住んでいる京都市では、家庭の使用済みてんぷら油や飲食店の廃食用油を回収してバイオディーゼル燃料を生成し、市バスやごみ収集車の燃料に用いていると知りました。温室効果ガスの削減と言うと地球規模の壮大な話のようですが、身近でもこのような取り組みがなされているとは驚きました。
先日まで開催されていた大阪・関西万博では、生ごみを発酵させて作ったバイオガスを発電に生かす技術が紹介されていました。このような技術がさらに発展し、温室効果ガスの排出を減らしていける未来に期待しています。普段環境について考える機会はなかなかありませんが、ニュースをきっかけに、自分も資源の無駄遣いをしないようにしなければと感じました。今回のCOP30では、有効な合意がなされるのでしょうか。注目しています。
参考記事
11日付 読売新聞朝刊(大阪13版)1面 「温室ガス削減 協調争点」関連記事2、3面
6日付 日経新聞電子版「COP30首脳級会合が開幕 米国不在の温暖化対策、主役狙う中国」
8日付 日経新聞電子版「COP30、水素やバイオ燃料「10年で4倍」宣言 ブラジルや日本が提案」
11日付 日経新聞電子版「タイの温暖化ガス削減を日本に還元 環境相発表、COP30参加も表明」
参考資料