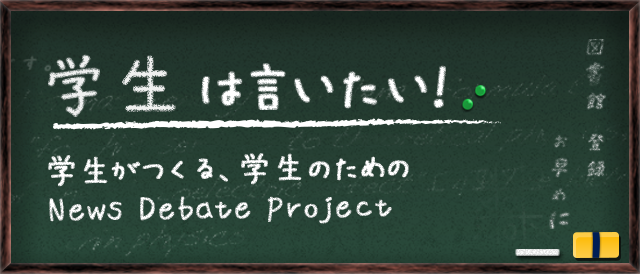この季節になると、4年前の今ごろ、地元・秋田の美容室で上京前に髪を切ってもらったことを思い出す。小さい頃から知っている60代の女性美容師は「東京に行く前にかっこよくしてあげる」とはりきって、受験中に伸ばし放題になった私の髪を整え、笑顔で送り出してくれた。その彼女は、数年前にがんで亡くなった。
大学生のうちに、近しい人びとの訃報に接することが何度かあった。祖母亡きあとは長い間ひとり暮らしだった祖父。お世話になった高校時代の担任。一緒に成人式を迎えられなかった中学の同期生。かなり限られた範囲の交流しかなかった人もいるのに、どういうわけかその死に気持ちが沈んだ。
精神科医の野田正彰は、自著『喪の途上にて』の中で、アメリカのエリック・リンデマンの論文からいくつかの「正常な悲哀」の反応をまとめている。その中に「死んだ人のイメージに心が満たされてしまうこと」があった。「故人のイメージが頭を占めてしまい、感覚全体がなんとなく変ってしまう。非現実のか細い感覚、他人から感情的に遠くにいるような感じになる」のだという。
亡くなる直前の姿よりも、彼らが生きていた頃のイメージがくりかえし頭の中で流れる。棺の中の姿はもうぼんやりとしか思い出せないけれど、生前の相手の顔つきや目の輝き、交わした言葉などは色をもった記憶として今も残っている。
生きる、ということは誰かの記憶に残ることでしょう?そういう意味で、息子の生き方はぼくの心に刻まれていて、いまを生きる支えになっています。
息子を亡くしている政治学者の姜尚中さんのことばが、今日の朝日新聞に載っていた。人びとの死は、その人が生きていた重みを明らかにする。それは強い力をもっていて、自分はそれに引きずられやすくなっているのかもしれない。
姜さんはまた、「自由」について次のように語っている。
大切なのは時代や世代という「設え(しつらえ)もの」から離れ、自分なりの価値観で生きること。
きのう会った一つ上の先輩は、「会社に入ったら目の前のことをこなしていくことに一生懸命になり、いつのまにか呑みこまれている」というようなことを言っていた。
「自分なりの価値観」だけでは無理が出ることもあるし、それは絶えず変わり続けるものだ。しかし、簡単には曲げたくないものもある。そのために、何者にも侵されない余白を心の中に残しておきたい。これまで出会った人たちとの、ふとしたときに心を温めてくれる思い出も、そこにしまっておきたい。
―――
あらたにすでの投稿は今日が最後になります。自分の考え方や文章のクセを知るいい機会になりました。サイトを訪れてくれた読者の皆さまに心より感謝申し上げます。またどこかでお目にかかれるように頑張ります。
参考記事:29日付 朝日新聞朝刊(東京12版)32面(文化・文芸)「語る―人生の贈りもの― いまようやく、自由になった 政治学者 姜尚中」
引用文献:野田正彰『喪の途上にて―大事故遺族の悲哀の研究―』(岩波書店,1992)81-84.