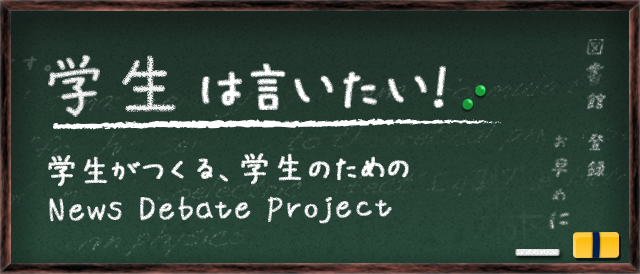3月8日は国際女性デーでした。当日の朝刊には性別に関連した社会問題の特集記事が多くみられ、どれも興味深かったです。今回は女性の健康とキャリアについて考えたいと思います。
終戦直後の女性の平均寿命が54歳であったのに対して今は87歳。生涯で経験する月経回数は、何人も子どもを産み育てた昔の女性が約50回だったのに対し、今は平均450回前後と、9倍に増えているそうです。そのため、子宮内膜症など月経関連の疾患や閉経後の体調変化への対応が重要になってきています。
記事の中で保健師は「定期的に検査し早めに必要な治療を受けることが将来のコンディション維持につながる。主治医を見つけて通える職場環境作りを進めたい」と話しています。
先日、子宮頸がんワクチンを接種するために産婦人科を訪れた時のことが印象に残っています。平日だったのですが、午前中の受付終了時間が迫った正午前には待合室の椅子がすべて埋まるくらい混み合っていました。隣の椅子に座っていた人が受付のスタッフに「1時から仕事があるので、可能であれば早めに診てもらいたい」と申し訳なさそうに話している声が聞こえました。
その人がどのような目的で通院していたのかはわかりませんが、限られた時間の中で通院することの難しさという社会人が直面する現実を感じさせるやりとりでした。筆者はまだ大学生であるため時間の制約やストレスなく通院することができます。対して社会人は仕事の合間を縫って予約を取っている人が多いのかと思われます。病院の混み具合やその日の診察状況によっては時間が押してしまうこともあるでしょう。
筆者は今回のワクチン接種が3回目で規定の回数を終了しました。医師からは「体内の変化は自分では気づきにくいこともあるので、今後も定期的に検査を受けることをお勧めします」と言われました。身体の中の変化は自分でも気づきにくい部分があると思うので、病院での診察は優先度の高いものだと思っています。
しかしながら先にも述べたように、社会人にとっては予約を取れる時間帯に制約があるうえ、予定していた時間枠で診察を受けられないリスクもあります。こうして働きながら通院するハードルが高くなっているのではないでしょうか。定期的な診察が重要とわかっていながらも、なかなか難しい状況が続いています。
2024年の内閣府の調査報告によれば、「女性特有の健康課題に対して職場にどのような配慮があると働きやすいか」との質問に対し、20〜39歳の女性では「生理休暇を取得しやすい環境の整備」と答えた割合が28.1%に達し、最も高い項目でした。企業によっては男性社員が生理痛を知る研修もあり、社会全体で女性特有の悩みを理解しようとする動きが広がっているとも言えるでしょう。
記事の中でも紹介されていたように「主治医を見つけて通える職場づくりを整えること」や「生理休暇ではなく『健康休暇』なら取りやすい」という声を取り入れ、健やかに働ける体制や周囲の人に身体のことを相談しやすい環境を整えていきたいものです。
参考記事
3月8日付 朝日新聞(大阪14版)18面 『話そう未来に向けて 産婦人科検診通いやすい職場を』
参考資料
朝日新聞デジタル 「生理痛の痛み、VR装置体験 広がる企業研修 100社以上で実施」https://digital.asahi.com/articles/DA3S16127909.html?iref=pc_ss_date_article
男女共同参画局 「特―67図 女性特有の健康課題に対して、どのような配慮があると働きやすいと思うか(男女、年齢階級別)https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r06/zentai/html/zuhyo/zuhyo00-67.html