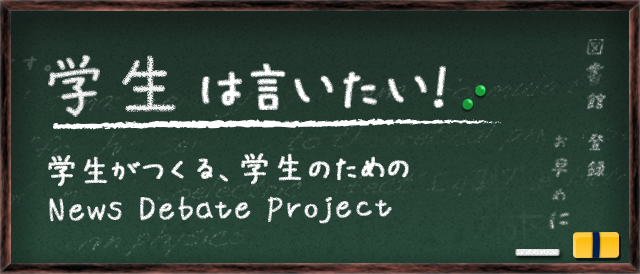西武線清瀬駅からバスに揺られて15分。自然豊かな景観の中に国立療養所多磨全生園はあります。『ハンセン病文学の新生面「いのちの芽」の詩人たち』がハンセン病資料館の企画展として開催されているため、訪れました。
「いのちの芽」は1953年、全国の8つのハンセン病療養所から73人が参加して編まれた初の合同詩集です。今回の企画展では、テーマを8つほどに分類した上でさまざまな詩を抜粋して紹介しています。展示室に入ってすぐのコーナーでも解説されていますが、この詩集を貫くテーマは「ニューエイジ」でした。戦後の詩のみを収録し、戦前の諦念を中心とした暗い雰囲気を払拭する思いが込められていたそうです。
詩を1つ1つ鑑賞していくうちに、気づいたら涙が溢れてしまう作品に出会いました。島比呂志さんの詩「ふるさとの家を思う」です。故郷・家族のコーナーに掲げられた作品には、新薬が開発されたことで明るさを取り戻した家族に、治療の効果が上がらないことを伝えられない心情が綴られています。家から引き離され、独り闘病する中でも、家族に迷惑をかけたくない、という配慮。普遍的な思いやりが溢れています。きっと話した方が楽になるのに、迷惑をかけたくないからこそ孤独が深まる。そんな姿が浮かび上がります。
厚木叡さんの「伝説」は、不条理の中でも内面の美しさが光る人間への愛が感じられる詩。こちらも強く心に残りました。
戦後のハンセン病文学には、人間らしさがありありと描かれている魅力があると思います。彼らが目指したのは、諦念から踏み出し、ありのままの気持ちも発信することでした。
ハンセン病によって身体が不自由になることへの恐怖や喪失感。家族や妻を思う温かな気持ち。人から向けられる嫌悪や隔離政策による孤独と悲しみ。ハンセン病政策への怒り。どうにもならない不条理を受け入れながらも、微かな喜びを見つける明るさ。本当に様々な詩が紹介されていました。筆者はこの展示を後にした後、気持ちが大きく揺れ動いていました。非常に価値のある経験です。
文学は、現代では「いらない」、だとか「なくても死なない」とか言われることが時折あります。でも、人生ってままならないことばかりだと思います。自分の思う通りになんでも快適に過ごせて、感情の揺らぎが一切ない世界だったら必要ないかもしれません。でも長い人生、不条理なことに出遭ったり、思わぬ感情が噴き出したりすることもあるでしょう。それは、コントロールできません。
そんな時、溢れる想いや感情を誰かに伝えたくてものを書きますし、自分のために綴ると思います。そしてなにより、他者の文章からは気づきを与えてもらえる。ハンセン病文学も、人生がままならない辛さの中で生まれた素直な感情がそのまま描かれているからこそ、読み手がいま感じている痛みに静かに響くのだと思います。文学は、そういった強い力がある。
資料館を後にする時、受付の方と本当に少しだけですが、お話をしました。学芸員の方が問題意識を持ちながら企画展をつくっている、と教えてもらいました。時間をかけて丹念に準備をしているのです。文学の価値を再認識できたのは、文化を守る担い手のみなさんの存在も大きいことを実感しました。この空間が今後も守られていってほしい、そして自分も次世代に繋げていきたい、そう思いながら帰りのバスに揺られていました。
【参考資料】
国立ハンセン病資料館公式サイト(企画展の詳細や関連イベントのお知らせが掲載されています)
https://www.nhdm.jp/events/list/4942/
※写真は撮影可能な部分のみを使用しております。
追伸
大学卒業に伴い、今年度であらたにすを卒業いたします。拙い文章でしたが、今までお付き合いいただき誠にありがとうございました。今後もあらたにすをよろしくお願いいたします。