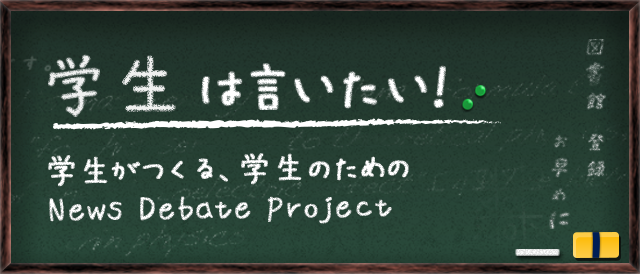広島への原爆投下から77年。8時15分、広島の平和公園で黙祷のための鐘が鳴らされる映像に、戦争へ思いを馳せる。自分にできることは何だろう。そう考えると、やはりあの日のことを忘れないということしかない。そこで原爆文学の金字塔である『夏の花』を初めて読んだ。
この作品の解説では、よく「抑制」や「静謐」という言葉が用いられている。戦争や原爆を題材にした作品のイメージとは合わないような気がするが、読むとその意味がよくわかる。
男であるのか、女であるのか、殆ど区別もつかないほど、顔がぐちゃぐちゃに腫れあがって、随って眼は糸のように細まり、唇は思いきり爛れ、それに痛々しい肢体を露出させ、虫の息で彼らは横たわっているのであった。私たちがその前を通っていくに随ってその奇怪な人々は細い優しい声で呼びかけた。「少し水を飲ませて下さい」とか、殆どみんながみんな訴えごとを持っているのだった。(岩波文庫 小説集夏の花 p18より)
これだけでは、抑制や静謐がわかりにくいだろうか。では、作者の原民喜が残した『水ヲ下サイ』という詩を紹介したい。
水ヲ下サイ アア 水ヲ下サイ ノマシテ下サイ 死ンダハウガ マシデ 死ンダハウガ アア タスケテ タスケテ 水ヲ 水ヲ ドウカ ドナタカ オーオーオーオー オーオーオーオー 天ガ裂ケ 街ガ無クナリ 川ガ 流レテヰル オーオーオーオー オーオーオーオー 夜ガクル 夜ガクル ヒカラビタ眼ニ タダレタ唇ニ ヒリヒリ灼ケテ フラフラノ コノ メチヤクチヤノ 顔ノ ニンゲンノウメキ ニンゲンノ
こうして比べると、恐ろしいほど淡々と書かれていることがわかってもらえるだろう。いやむしろ、見たままを丁寧に描写したことで、ありありとこの惨事が伝わってくるのかもしれない。
ただ、そんな文体に不思議な力がある。特に印象に残った3つの場面を紹介したい。
「死んだ方がましさ」と吐き捨てるように呟いた。私も暗然として肯き、言葉は出なかった。(岩波文庫 小説集夏の花 p19より)
ここでは誰かが、絶えず死んで行くらしかった。(岩波文庫 小説集夏の花 p25より)
次兄は文彦から爪を剥ぎ、バンドを形見にとり、名札をつけて、そこを立去った。涙も乾きはてた遭遇であった。(岩波文庫 小説集夏の花 p26より)
1つ目からは言葉にならない「叫び」が、2つ目からはどこか「絶望」が、3つ目からは底知れない「憤り」が感じられる。どれも本文では1から2行程度の短い文章だが、鮮烈な体験をしたことで、自分の中の何かが超えてはいけない一線を超えた人にしか書けない文章のように思えてならない。
当初『原子爆弾』という題名だったこの作品は、GHQの検閲を経て慎ましく目立たない『夏の花』に変更されて世に出ることになるが、この題名で良かったのではないか。冒頭に描かれた作者の妻への墓参りで、夏の花を添えるシーンが作品全体を通底する「祈り」の原点であるように読めるからである。私たちもいつまでも、原爆で亡くなった方に心の中で花を手向け、祈り続けていきたい。あの日を決して忘れないように。
参考記事:
6日付 朝日新聞朝刊 23面(読書) 「あの日の体験 読み直すとき」
参考資料:
原民喜, 小説集夏の花, 岩波文庫, 1988